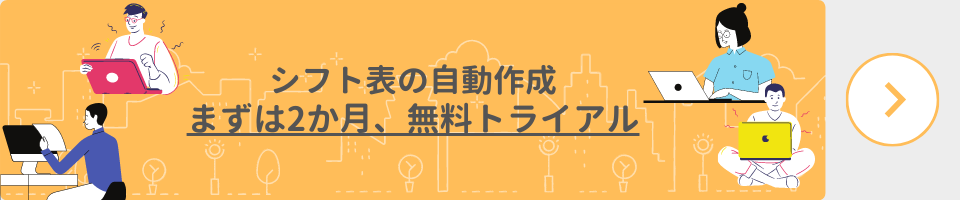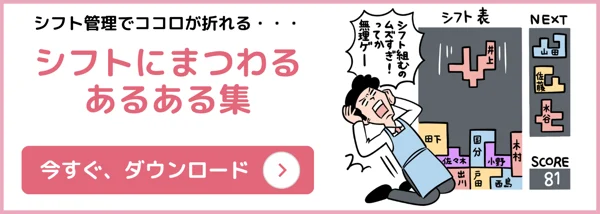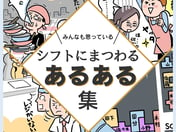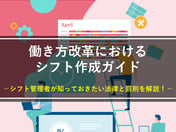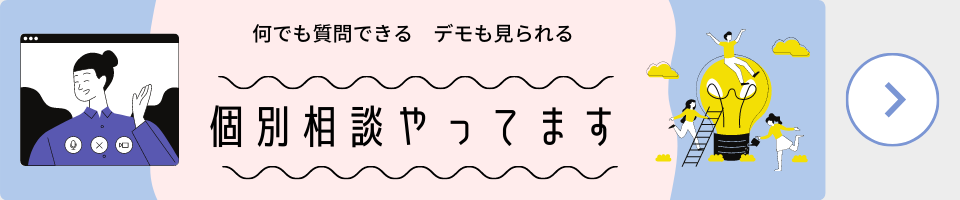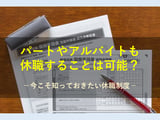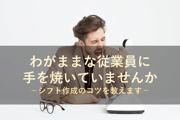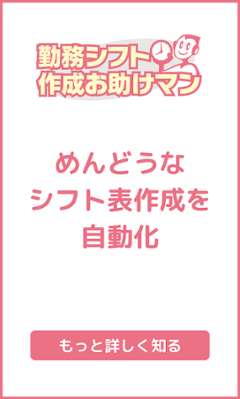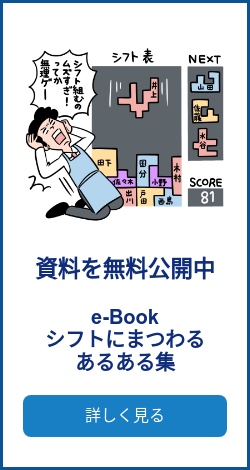24時間労働の注意点

24時間労働の実施においては、いくつかの重要なポイントを押さえておきましょう。以下に注意すべき点をあげます。
36協定の締結
36協定とは、1日の労働時間である8時間、週40時間という上限を超えて従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に、事業主と労働者の代表者(労働組合など)の間で結ぶ協定のことです。この協定は、労働基準法36条に基づいているため、「36協定」と呼ばれています。
24時間体制の職場では、緊急対応など時間外労働や休日労働が発生しがちです。24時間労働を導入する際には必ず36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが法律で義務付けられています。
そこで時間外労働の上限(月45時間、年360時間など)、休日労働日の回数、深夜労働の条件などを定めます。
仮眠時間が労働時間にあたる場合がある
24時間労働においては、仮眠時間が労働時間として認められる場合もあります。これは、業務から完全に解放されているか否かによって判断されるのが一般的です。
業務から完全に解放されていなければ、たとえ仮眠中であっても労働時間とみなされます。具体的には、仮眠中に業務への復帰が求められ、職場内または指定された場所でのみ仮眠できる状況などが該当するでしょう。
シフト管理者は労働基準法に基づき、労働者の職務内容や拘束条件を詳細に検討し、仮眠時間が労働時間として認められる可能性のあるケースを把握しておくことが重要です。
待機時間が労働時間にあたる
待機時間も、状況によっては労働時間とみなされることがあります。待機時間が労働時間にあたるかどうかは、労働者が使用者の指揮命令下にあるかどうかというのが判断基準になります。
緊急事態や業務上の必要に応じて、いつでも呼び出しに応じなければならない状況にある場合、または特定の場所に拘束される場合は実質的に労働者が使用者の指揮命令下にあるとみなされ、労働時間と判断される可能性が高くなります。
また業務開始前や終了後に、机の整理整頓や翌日の準備など業務に関連した作業を行っている場合も同様です。
複雑になる給与の計算方法
24時間労働では、時間外労働、休日労働、深夜労働などが複雑に絡み合い、給与計算が非常に煩雑になるため注意が必要です。
変形労働時間制では、1日ごと、1週間ごと、あるいは一定期間ごとの総労働時間を算出し、その時間が法定労働時間を超えていた場合超過分が時間外労働とみなされます。そして時間外労働には、労働基準法で定められた割増賃金を支払わなければなりません。
特に深夜労働や休日労働は通常の労働時間とは異なる割増率が適用されるため、時間帯ごとの労働時間を正確に把握し、それぞれの割増率を適用して計算する必要があります。
24時間労働における給与計算は複雑で、専門的な知識や計算ツールが必要となるケースも少なくないでしょう。
あわせて読みたい記事
【2025年版】シフトと労働基準法|違法にならないシフト作成のルールを専門家が解説
24時間労働が違法になる場合とは

24時間労働は、労働基準法に基づいた条件を満たした上で実施されなければ違法となる可能性があります。
不適切な運用は、単なる管理ミスでは済まされません。労働基準監督署から是正勧告を受けるほか、罰則として6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。それぞれ詳しく説明していきます。
残業代が未払い
残業代は、労働基準法で定められた1日の労働時間(原則8時間)や1週間の労働時間(原則40時間)を超えて働いた場合に支払われます。
| 項目 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(8時間を超える労働) | 25%以上(月60時間を超える部分は50%以上) |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
| 深夜労働(22時~翌日の朝5時) | 25%以上 |
法定労働時間に基づいて、残業代は原則としてこのように算出されますが、これらの条件が重なるとさらに割増率は高まります。
| 項目 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働+深夜労働 | 50%以上(月60時間を超える部分は75%以上) |
| 深夜労働+休日労働 | 60%以上 |
このように、割増賃金の計算は条件によって複雑になりますが、たとえ故意でなくとも正しく支払われないと違法となります。
安全配慮義務に違反している
労働者の安全確保も、使用者(企業側)に課せられた法的義務です。労働契約法第5条において、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、使用者が配慮しなければならないとされています。
24時間労働は、基本的に労働時間が長く勤務パターンも不規則であるため、労働者の健康に悪影響を及ぼすリスクを伴います。
このような労働災害や健康障害を防ぐため、疲労を回復できる休憩時間の確保、定期的な健康診断、休日取得の奨励、作業環境の整備、危険物の管理などが必要です。安全に働くための配慮に欠けることは法律違反となります。
法定休日を与えない
労働基準法では、1週間に1日または4週間に4日の法定休日を与えることが義務付けられています。これは労働者の健康を守り、長時間労働による疲労を回復させるための重要な制度です。
24時間労働を含む勤務が連続し、法定休日が確保されない場合には労働基準法違反とみなされます。
このような状況が続くと、労働者の健康や生活への悪影響が懸念され、結果的に労働生産性の低下や離職につながる可能性もあるからです。そのため、シフト管理においては、勤務スケジュールを慎重に組み立て、法定休日が確実に守られるよう管理しましょう。
24時間労働と2交代制・3交代制の違い

24時間稼働が求められる職場では、勤務体制として2交代制や3交代制が採用されているのが一般的です。これらの勤務形態は、労働者に適切な休息時間を確保しつつ、24時間の稼働を維持するために設計されています。
24時間労働が一人の労働者に過度な負担を強いる可能性があるのに対し、交代制勤務は複数の労働者でシフトを分担する仕組みです。この章では、2交代制と3交代制の仕組みや特徴について詳しく解説します。
2交代制とは
2交代制とは、1日24時間を2つの勤務時間帯に分けて労働者が交代で勤務する体制です。一般的に、1つのシフトは12時間程度となり、これを日勤と夜勤に分けて運用します。この勤務形態は、医療、製造業、警備業など、24時間稼働が求められる職場で採用されることが多いです。
2交代制の最大の特徴は、一人の労働者が1日に長時間勤務するため、シフト終了後の十分な休息時間が必要になる点です。労働基準法に従い、休憩時間や休日を適切に設定し労働者の健康管理を行うことが求められます。また、深夜帯での勤務が含まれるため、深夜手当が発生し、割増賃金の支払いも必要です。
3交代制とは
3交代制とは、1日24時間を3つの勤務時間帯に分け、労働者が交代で勤務する体制です。通常、1つのシフトは8時間程度となり、日勤・準夜勤・深夜勤といった形で運用されます。この勤務形態は、医療現場や製造業などで多く採用されています。
3交代制のメリットは、1回の勤務時間が短いため、2交代制に比べて労働者への負担が軽減される点です。また、労働時間が比較的均一であるため、安定した生活リズムを維持しやすいという特徴があります。
ただし、シフトごとに勤務時間が変動するため、生活リズムが乱れる可能性がある点には注意しましょう。また、深夜手当や時間外労働に関する適切な賃金計算が求められます。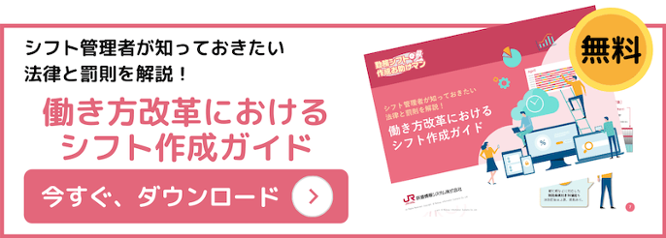
まとめ

24時間労働は、勤務形態を適切に管理しないと法令違反や労働者の健康リスクにつながる可能性があります。労働基準法を遵守しつつ効率的なシフト管理を実現するためには、シフト管理システムの導入が非常に有効です。
シフト管理システムは複雑な24時間労働のスケジュールを簡単に作成・修正できるほか、勤務時間を視覚的に把握しやすくなり、働き過ぎや休息不足などを未然に防げます。
給与システムと連携すれば、割増賃金など複雑な計算も効率化するでしょう。24時間労働の管理を軽減するためにも、シフト管理ツールを検討してみてはいかがでしょうか。