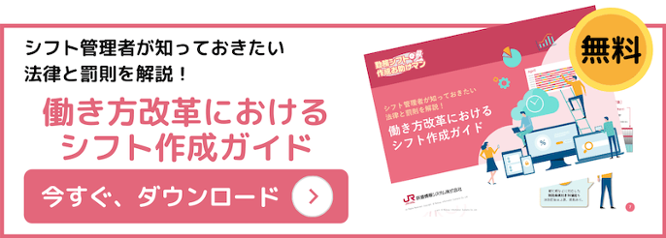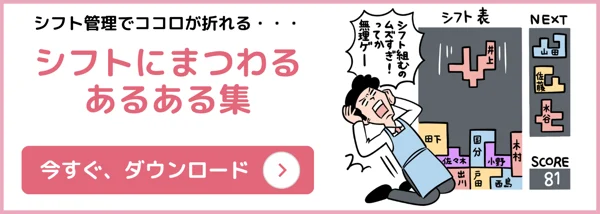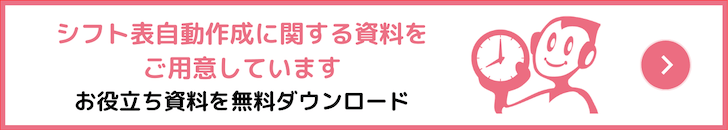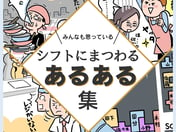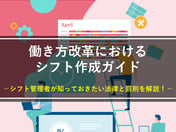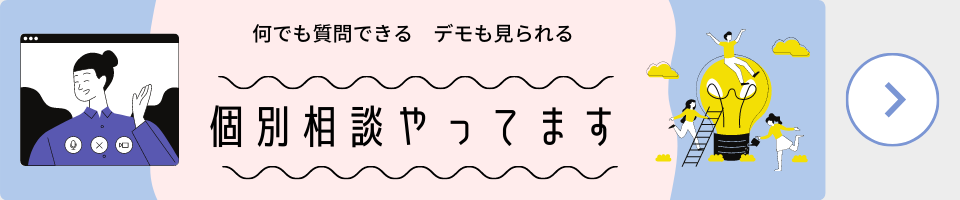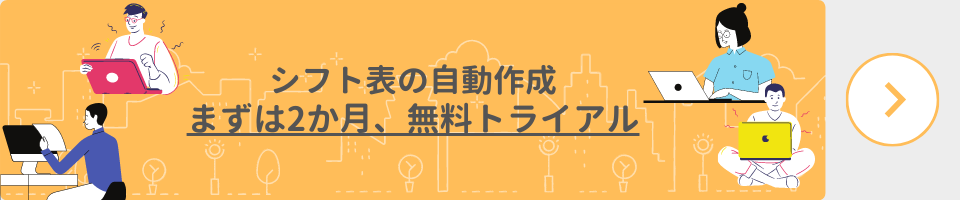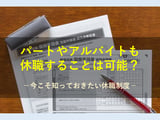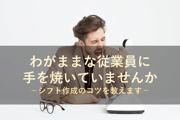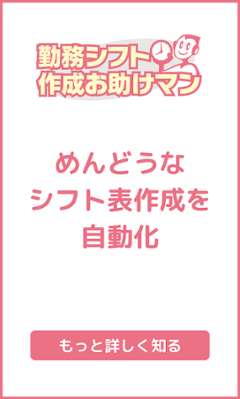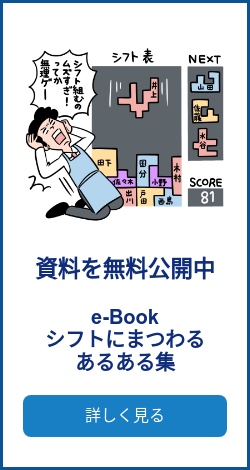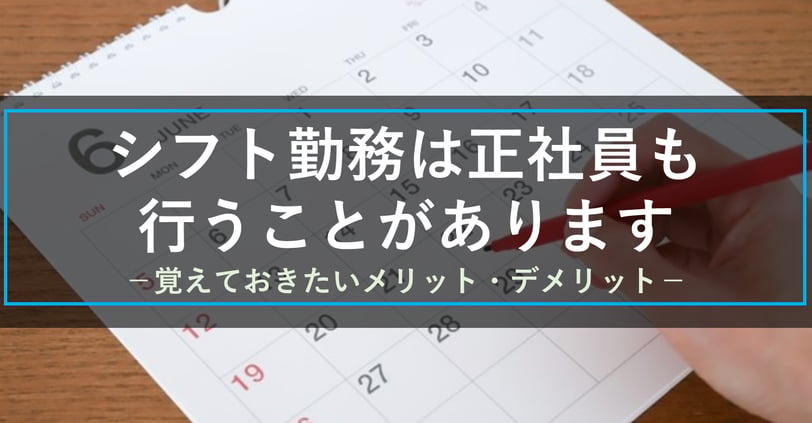
シフト制の働き方は、短時間勤務のパートやアルバイトのほか、正社員にも取り入れられています。シフト制の働き方は、休日の曜日が固定していないほか、出勤日によって出勤時間が異なるため、変則的な点が特徴的です。しかし、ほぼ毎日、長時間にわたって営業している企業や店舗にとっては、シフト制にすれば人員を手配できるため、多くの企業で導入しています。
正社員のシフト制は主にどんな業種で取り入れられているのでしょうか。そのほか、正社員がシフト制で働いている場合のメリット・デメリット、シフトを作成するときに気をつけたいポイントについてもみていきます。
- シフト制とは
- 正社員もシフト制で働く どんな業種で導入されている?
- シフト制で働くメリット
- シフト制で働くデメリット
- シフト制の正社員は休日希望を出して休みを取れる?
- 正社員のシフトを作成するときに気をつけたいポイントは?
- まとめ
シフト制とは
シフト制とは、休日や働く時間帯が一定ではない働き方のことで、現代の労働環境において非常に一般的な働き方です。休日や働く時間帯が一定ではないため、柔軟な働き方が可能となります。
正社員の労働時間は通常、1日あたり8時間と定められていますが、営業時間が長い企業では、業務の開始から終了までの時間はほとんどの場合8時間を超えます。このため、職種によっては正社員もシフト制で働くことがあります。シフト制では、勤務日ごとのシフトと勤務時間別のシフトの2つの要素が考慮されます。
勤務日ごとのシフトは、スタッフの出勤日や休日に関する要素です。一方、勤務時間別のシフトは、スタッフの勤務区分を指します。早番、中番、遅番などの勤務形態があり、それに基づいてシフトが作成されます。
シフトを作成する際には、まずはじめにスタッフの出勤日を決めます。また、営業時間が長い事業所や店舗では、スタッフがどの勤務区分になるかも決める必要があります。これにより、シフトが作成され、1か月分のシフト表にまとめて掲載されます。
ただし、正社員の勤務時間が8時間を超えない事業所や店舗では、勤務形態を決める必要はありません。その場合、スタッフの出勤日を決めるだけでシフトが完成します。
また、週5日を超えて営業する事業所では、休日の確保が重要です。正社員は週に2日の休日が必要ですが、月曜日から土曜日まで業務を行う事業所では、休日は日曜日のみとなります。もう一日の休日は他の曜日に取得することができるため、休む曜日を決めるためにシフト制が導入されます。
シフト制は、労働時間の柔軟性や労働者の希望に合わせた働き方を実現するための重要な制度です。事業所や店舗の営業時間や労働条件に応じて、適切なシフトが作成されることで、効率的な勤務管理が可能となります。
正社員もシフト制で働く どんな業種で導入されている?
正社員の働き方にシフト制を導入している業種としては、下記があげられます。
- 小売業や飲食業など、営業時間が長い業種
- 月曜日から土曜日まで営業する事業所
- 医療機関・工場など24時間体制で交代勤務を行う業種
・2交代の働き方
・3交代の働き方
・警察や消防の交代制
具体的な業種については次の項目で説明します。
小売業や飲食業など、営業時間が長い業種
営業時間が長い業種の例としては、小売店や飲食店などがあげられます。スーパーやドラッグストアなど、小売店の多くは朝から夜まで営業しています。また、飲食店はお昼前に営業を開始し、夜遅くまで営業するケースがほとんどです。これらの業種で開店から閉店まで勤務すると、労働時間は8時間を大きく上回ってしまうため、正社員が開店から閉店まで業務を続けると大幅な長時間労働となってしまいます。正社員の労働時間を8時間以内に抑えるために、これらの業種ではシフト制を導入しています。
例として、朝から夜まで営業しているスーパーのシフトは下記のようになります。なお、下記のシフトは休憩時間を1時間含みます。
- 早番:7時~16時
- 中番:10時~19時
- 遅番:15時~24時
上記のようなシフトを組むことにより、開店前から閉店後まで常に社員がいる形となります。また、中番の人が出勤している時間帯は正社員の数が多くなるため、日中の忙しい時間帯であっても十分に対応できます。このように、シフト制によって人員を割り当てることによって、適正な人員で企業や店舗の運営が可能となります。
さらに、シフト制は労働者の負担を軽減するだけでなく、労働環境の改善にも繋がります。例えば、従業員同士の連携やコミュニケーションを促進することで、業務の効率化やストレスの軽減につながります。また、休日や休暇の希望にも柔軟に対応できるため、従業員のワークライフバランスの向上にも寄与します。
このように、営業時間が長い業種ではシフト制が重要な働き方の一つとなっています。労働時間の制限だけでなく、従業員やお客様のニーズを考慮した柔軟な働き方を実現することで、より良い労働環境と顧客満足度の向上を図ることができます。
月曜日から土曜日まで営業する事業所
正社員として働く医療事務や薬剤師は、月曜日から土曜日まで営業するクリニックや調剤薬局などの事業所では、シフト制の働き方が一般的です。このシフト制度は、労働基準法による1週間の労働時間制限が関係しています。正社員の場合、通常は1日8時間勤務となるため、5日間働いた時点で1週間の労働時間が40時間に達します。
つまり、月曜日から土曜日まで営業している事業所で働く正社員は、日曜日以外にもう一日休む必要があります。休みの日は、週の真ん中にあたる水曜日や木曜日などに入れることもできますし、月曜日や土曜日に休みを取ることで日曜日と連休を作ることもできます。
ただし、具体的にどの曜日に休みを取るかは、シフト管理者が作業内容に応じて決めていきます。もし、休日の希望がある場合は、1か月のシフトが作成される前にシフト管理者に要望を伝えると対応しやすくなります。
このようなシフト制度は、医療事務や薬剤師などの正社員にとって、柔軟な働き方を可能にします。また、休みの日を工夫することで、連休を取得することもできます。労働基準法に基づいた労働時間制限を守りつつ、効率的に働きながらメリハリのある生活を送ることができるのです。
医療機関・工場など24時間体制で交代勤務を行う業種
24時間体制で交替勤務を行う業種としては、24時間操業している工場、警察や消防などのほか、病院に勤務する看護師も24時間体制で勤務を行っています。交替勤務は2交替と3交替に分けられます。それぞれの交替制について下記で説明します。
1) 2交替の働き方
2交替では、日勤と夜勤に分かれます。単純に12時間程度で分けるほかにも、日勤は8時間勤務、夜勤は仮眠込みで16時間勤務という形で分ける方法があります。なお、16時間勤務のように、当日の日中から翌朝にかけての勤務を「当直」と呼ぶこともあります。
2交替のシフト例は下記の通りです。いずれも休憩時間を1時間含みます。
- およそ12時間で分ける場合
日勤:8時~20時30分
夜勤:20時~翌朝8時30分
(補足)勤務時間が12時間30分として、30分間で引き継ぎを行う場合あり - 日勤と当直で分ける場合
日勤:8時~17時
当直:16時~翌朝9時
(補足)勤務時間が重なっているタイミングで引き継ぎを行う
2交代制は3交代制と比べると勤務時間が長くなります。特に、夜勤の場合は拘束時間が16時間程度になるため、慣れない間は勤務が非常に長く感じられます。ただし、拘束時間が16時間程度の場合は、1時間の食事休憩のほか、2~3時間程度の仮眠時間が設けられるため、働きやすいように配慮されています。また、実際の勤務時間は12~13時間程度となります。
2) 3交替の働き方
3交代では、早番、中番、遅番に分けられます。なお、医療機関では早番を日勤、中番を準夜勤、遅番を夜勤と呼ぶこともあります。早番は日中の勤務、中番は夕方から夜遅くの勤務、遅番は深夜から朝方にかけての勤務となります。
3交代のシフト例は下記の通りとなり、いずれも休憩時間を1時間含みます。勤務が重なっている時間帯に引き継ぎを行います。
- 早番:8時~17時
- 中番:16時~深夜1時
- 遅番:0時~翌朝9時
3交代制の勤務時間は原則として8時間となるため、2交代制と比べると勤務時間は短めに抑えられます。ただし、出勤のパターンが3種類あり、場合によっては夜の遅い時間に出勤しなければならないため、生活リズムが崩れやすくなることもあります。
3) 警察や消防の交替制
警察や消防の交替制は、上記で説明した2交替制や3交替制とは異なり、独自の交替制シフトが組まれています。働き方の例としては、勤務時間が約16時間、拘束時間は24時間となります。
シフトの例をあげると、出勤時間は朝9時、勤務が終了するのは翌朝9時です。勤務は長時間にわたるため、休憩は昼食休憩、夕食休憩、随時小休憩のほか、深夜に4~5時間程度の仮眠の時間が設けられています。
勤務が終了した日は「非番」となり、多くの場合は翌日が公休となります。また、公休日の次の日は主に当直となり、当日から翌朝までの勤務となります。
シフト制で働くメリット
初めてシフト制の働き方をする場合なら、シフト制で働くメリットやデメリットについて理解しておきましょう。シフト制で働く主なメリットとしては下記があげられます。
- 平日に休める
- 出勤の時間帯とラッシュが重ならないことも
- 2~3日働けば休める場合も
それぞれのメリットについて説明します。
平日に休める
シフト制で働くメリットは、平日に休めることです。平日なら店舗やレジャー施設が空いているため、買い物やレジャーをゆっくりと楽しめます。また、市役所や銀行や病院など、平日にしか業務を行っていない店舗や施設にも行けるので、さまざまな用事を済ませられます。
一般的には、休みといえば土日や祝日というイメージが強いですが、シフト制の仕事で平日に休むようになると、土曜や日曜に休むよりも平日に休む方が利便性が高いと感じることがあります。
また、平日にしか業務を行っていない店舗や施設に行くこともできます。例えば、市役所や銀行、病院などは平日にしか営業していないことが多いです。シフト制の仕事で平日に休むようになれば、これらの場所に行くことができて、さまざまな用事をスムーズに済ませることができます。
出勤の時間帯がラッシュと重ならないことも
その日のシフトによっては早番ではなく、中番や遅番の日もあります。そのような日は朝に出勤する必要がないため、出勤の時間帯が通勤ラッシュと重ならずに済みます。朝の電車は混雑が激しいため、通勤するだけで疲れてしまうことも多々ありますが、中番や遅番の勤務で昼前、または午後から出勤する場合は電車が空いているので、余裕を持って出勤できます。
中番や遅番の勤務の特典の一つは、通勤時のストレスを軽減できることです。朝の通勤時間帯は多くの人が一斉に動くため、電車やバスは大変混雑します。そのため、早番で出勤すると、電車に乗るだけで疲れてしまい、一日の始まりから疲労感を抱えることがあります。しかし、中番や遅番の勤務で昼前や午後から出勤する場合は、電車が空いているので、ゆったりと座って出勤することができます。
2~3日働けば休める場合も
シフト制なら、2~3日働くと休みとなる場合が多いです。正社員は、原則として1週間あたり2回休むことができますが、シフト制の勤務は基本的に土曜や日曜は出勤となるため、休みは平日に2回取ることが多くなります。
例えば、ある1週間のシフトが下記の通りだとしましょう。
- 日曜日:出勤
- 月曜日:公休
- 火曜日:出勤
- 水曜日:出勤
- 木曜日:公休
- 金曜日:出勤
- 土曜日:出勤
この場合、公休日は月曜日と木曜日となるため、火曜日と水曜日の2日間働けば休みとなります。また、翌週の月曜日が休みなら、金曜日、土曜日、日曜日の3日間働くだけで済みます。シフト制ではなく平日5日間働く仕事の場合、月曜日の朝がゆううつに感じてしまいますが、シフト制で「2~3日働けば休める」と考えれば、休み明けの朝でも気持ちが楽に感じられることでしょう。
▼ あわせて読みたい記事
シフト管理者・シフト勤務者におススメのシステム・アプリ
自動作成を特長とするシフト管理システム|導入する前に知っておくべきこと
シフト作成に特化したシフト管理システム比較|クラウドのメリットとは
シフト制で働くデメリット
ここまで、シフト制で働くメリットについて説明してきましたが、メリットだけではなくデメリットもあります。主なデメリットは下記の通りです。
- 土日、お盆、年末年始などに連休を取りにくい
- ライフスタイルが乱れやすい
- 緊急対応が必要となる場合も
それぞれについて説明します。
土日、お盆、年末年始などに連休を取りにくい
シフト制で働く場合は土日の休みを取りにくいほか、ゴールデンウイークやお盆、年末年始などに連休を取ることは難しくなります。なぜなら、シフト制で働く場合は、土曜や日曜、お盆や年末年始などであっても通常通り仕事をしなければならないためです。
特に、小売業や飲食業は、お盆や年末年始はハイシーズンで忙しくなるため、正社員は原則として出勤しなければならないことを理解しておきましょう。
ライフスタイルが乱れやすい
シフト制で働くと、シフトに応じて出勤時間が変わることがあるため、ライフスタイルが乱れやすくなります。
たとえば、ある病院で2交代制を導入しており、看護師が下記のようなシフトで出勤するとしましょう。日勤の出勤時間は朝8時、当直の出勤時間は午後4時とします。
- 日勤→当直→公休→日勤→当直
上記のようなシフトだと、出勤時間が異なるだけでなく、夜に眠る時間も異なります。それにともなって、朝に起きたり、お昼ごろに起きたりする日もあるため、生活が不規則になりがちです。
生活が不規則になると身体だけでなく精神的にも疲れやすくなるため、毎日の仕事が負担に感じてしまうこともあるでしょう。日勤や夜勤を繰り返すシフトの場合、夜勤明けの日は午前中に眠っても昼過ぎには起きるなどして、可能な範囲で規則正しい生活に近づける方法で対応してみましょう。
緊急対応が必要な場合も
正社員でシフト制の働き方をしている場合、休みの日、または勤務が終了した後であっても緊急の対応をしなければならない場合があります。シフト制を導入している企業は営業時間が長いことが多く、土曜日や日曜日を含めてほぼ休まず毎日営業しているケースが多いです。見方を変えれば、正社員が休みの日でも会社は営業しているため、何らかのトラブルが発生すれば、急きょ緊急対応をするために会社に行かなければならないこともあります。
たとえば、飲食店でアルバイトの手配が全くつかない場合に、やむを得ず正社員が休日に出勤するケースがあげられます。緊急対応は極力発生させないことが重要ではありますが、さまざまな事情によってやむを得ず緊急対応をしなければならないこともあり得ます。
シフト制の働き方は、多様な事情に対応するための柔軟性を持っていますが、その反面、正社員が休みの日や勤務終了後にも緊急対応をしなければならないことがあります。例えば、シフトに空きが生じた場合や予定外のトラブルが発生した場合には、正社員が急遽出勤することが求められることがあります。
特に飲食店では、アルバイトの手配がつかない状況が生じることがあります。人手不足や急な欠員などが原因で、アルバイトスタッフが不足する場合、正社員が休みの日に自ら出勤するケースがよく見られます。休みの日であっても、お客様の要望やトラブルに対応するために、正社員の迅速な対応が求められるのです。
シフト制の正社員は休日希望を出して休みを取れる?
シフト制のメリットの一つに「休みを取りやすく、自分の都合のよいタイミングで働ける」ということがあります。パート、またはアルバイトの場合は、そのような働き方をしやすいですが、正社員の場合は原則として週5日は働かなければなりません。
そのため、正社員は希望した休みを取りにくいと考える人もいるのではないでしょうか。しかし、シフト制の正社員でも休日の希望を出して休むことは可能です。ただし、正社員の人数はパートやアルバイトと比べると少ないため、休日の希望が通った場合、他の正社員にとって負担となる場合があります。
そのため、シフト制の職場で働く正社員が休日の希望を出す場合は、1か月あたり2日程度に抑えておきましょう。これによって、他の正社員とのバランスを保ちながら、自分の希望を実現することができます。
また、シフト管理者は、来月分のシフトの作成を始める前に、スタッフに対して休日希望を出すように伝えます。スタッフの中で休日の希望がある人は、早めにシフト管理者に伝えておきましょう。これによって、シフトの作成に余裕を持たせることができます。
もし、休日希望の提出期限を過ぎてからシフト管理者に休日希望を伝えると、シフト管理者は既にシフトの作成を始めてしまっている場合があります。そのため、シフトを作成し直すことになり、他のスタッフにも影響が出てしまうかもしれません。なるべく早めに休日希望を提出することで、スムーズなシフト作成を支援しましょう。
シフト管理者によっては、休日希望の提出期限を過ぎたらスタッフの希望を受け付けない場合もあります。そのため、休日希望がある場合は、余裕を持ってシフト管理者に伝えましょう。早めの提出は、希望通りの休日を確保するために重要です。
シフト制の正社員でも休日の希望を実現することは可能ですが、その際には他のスタッフとのバランスを考える必要があります。希望を出す際には、他のスタッフに負担をかけないように注意し、シフト管理者とのコミュニケーションも大切にしましょう。自分の都合を大切にしながらも、チーム全体の円滑な運営を心がけることが大切です。
正社員のシフトを作成するときに気をつけたいポイントは?

正社員のシフトを作成するときに気をつけたいポイントは、無理のないシフトを作成することです。正社員のシフトを作成する場合、下記のようなシフトになってしまうことがあります。
- <第1週目>
- 日曜:公休
- 月曜:公休
- 火曜:出勤
- 水曜:出勤
- 木曜:出勤
- 金曜:出勤
- 土曜:出勤
- <第2週目>
- 日曜:出勤
- 月曜:出勤
- 火曜:出勤
- 水曜:公休
- 木曜:出勤
- 金曜:公休
- 土曜:出勤
上記のシフトの場合、1週間あたりの公休回数は2回となっていますが、第1週の火曜日から第2週の火曜日まで8日連続で出勤することになります。このようなシフトでは正社員にとって負担となってしまい、モチベーションが下がる原因になるだけでなく、疲れがたまって仕事中にミスをしてしまいがちです。
働きやすいシフトにするなら、下記のように変える方法があります。もともとは第1週の月曜日が公休でしたが、その公休を第1週の金曜日に移動しました。これにより、出勤は4日連続で済みます。シフトに基づいて業務を行う正社員の立場に立ち、無理なく働けるシフトの作成を心がけましょう。
- <第1週目>
- 日曜:公休
- 月曜:出勤
- 火曜:出勤
- 水曜:出勤
- 木曜:出勤
- 金曜:公休
- 土曜:出勤
- <第2週目>
- 日曜:出勤
- 月曜:出勤
- 火曜:出勤
- 水曜:公休
- 木曜:出勤
- 金曜:公休
- 土曜:出勤
まとめ
シフト制を導入することによって、企業は毎日の営業を確保するだけでなく、正社員の休みを交代制にすることで常に正社員が勤務できる状態を維持することができます。早番の正社員と遅番の正社員を配置することで、長時間の営業も可能となります。これにより、平日に仕事をして土日に休む正社員と比べると、シフト制の正社員は平日に休むことができ、さらに2~3日出勤すれば休みが取れることが多いため、休み明けの朝もスムーズに仕事に取り組むことができます。
また、多くの企業がシフト制を導入しており、シフト制の企業で働く機会も増えています。シフト制の企業に就職する際には、あらかじめシフト制の内容を理解しておくことが重要です。そして、シフト作成時のポイントとして公休週2回を例に挙げましたが、場合によっては連休を取得させる必要も出てくることがあります。
JRシステムが提供する「勤務シフト作成お助けマンDay」では、休みの勤務回数や連休の設定、勤務の並び等の勤務条件を考慮して、早番・遅番・夜勤等の「1日1記号を割り当てるシフト表」を作成することが出来ます。
本番利用時と同じ機能を2か月無料でトライアルできますので、システム化によって満足するシフト表作成が行えるかどうか、是非お試しください。