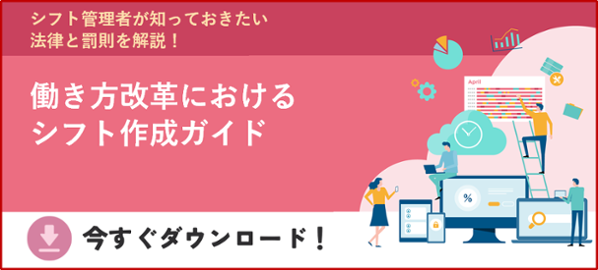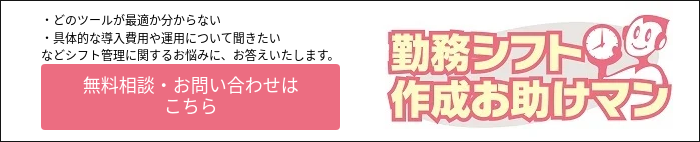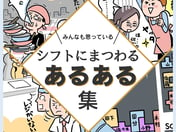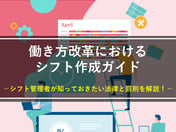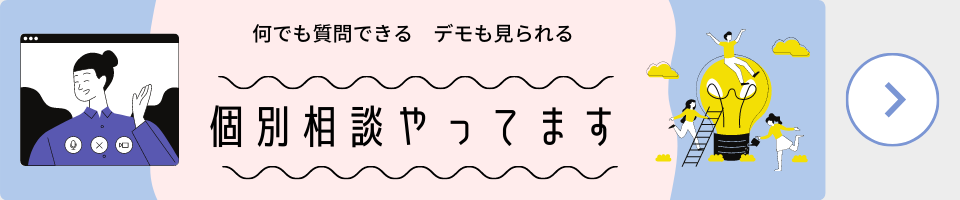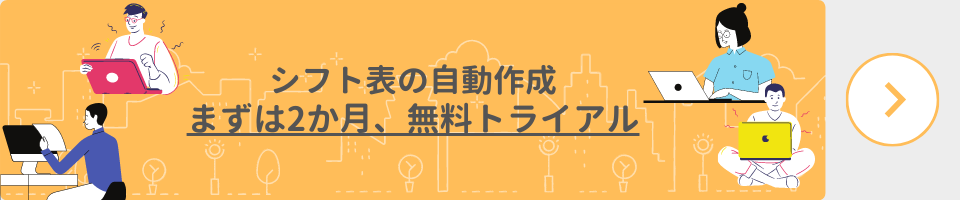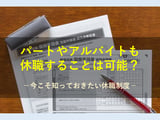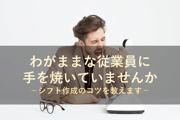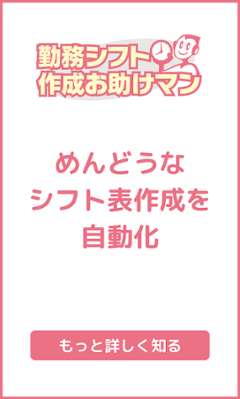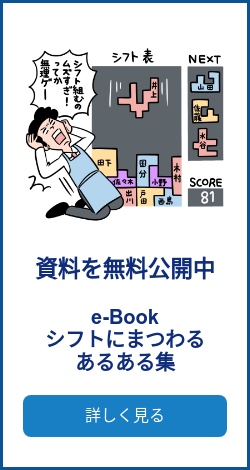「フレックスタイム制」は、自分の生活に合わせて出退勤の時間を決められる、とても魅力的な働き方です。一方で「チームの会議時間がなかなか決まらない」「急ぎの要件があるのに、担当者がまだ出社していない」といった、メンバー間の連携ですれ違いを感じた経験はありませんか?
個人の自由度を尊重しながらチームとしての生産性を維持するには、実は「シフト調整」の工夫が不可欠です。
この記事では、フレックスタイム制の基本や、シフト勤務との違い、具体的なシフト表の作成方法、便利なITツールなど、円滑な運用を実現するためのヒントを解説していきます。
制度をうまく使いこなしている企業の成功事例も紹介するので、自社のシフト調整を効率的かつ効果的に行うための参考にしていただければ幸いです。
- フレックスタイム制とシフト勤務の違いを正しく理解する
- フレックスタイム制でありがちな誤解と正しい運用方法
- フレックスタイム制のシフト表作成方法|実例とテンプレート
- フレックスタイム制とシフト勤務の併用は可能?成功事例も紹介
- フレックスタイム制が普及しない理由とその解決策
- フレックスタイム制導入の成功事例|柔軟な働き方を実現する方法
- 勤務シフト作成お助けマンで実現する効率的なシフト調整
フレックスタイム制とシフト勤務の違いを正しく理解する

「フレックスタイム制」と「シフト勤務」は、働き方の柔軟性という点で似ているように思われがちです。実は「働く時間の決定権が誰にあるか」という点で根本的な違いがあります。
フレックスタイム制は、労働者自身が日々の始業時間と終業時間を自主的に決定できる制度です。一方、シフト勤務は、会社側があらかじめ設定した複数の勤務時間帯(早番、遅番など)に労働者を割り当てる仕組みを指します。
つまり、時間の決定権が「個人」にあるのがフレックスタイム制で「会社」にあるのがシフト勤務というわけです。自由度の高さと、時間決定の主体がどこにあるのかが、両者を分ける最も大きなポイントとなります。
「なんちゃってフレックス」は違法?適法にするための条件と注意点
フレックスタイム制を導入しているはずなのに、実態は出退勤時間が固定されている…。そんな「なんちゃってフレックス」は、労働基準法に違反し、違法と判断される可能性があります。
フレックスタイム制を法的に有効にするには、就業規則への規定と、労使協定の締結が必要です。特に、コアタイムの時間設定には注意しましょう。
例えば、1日の所定労働時間が8時間なのにコアタイムが7時間に設定されているなど、労働者が自由に選択できるフレキシブルタイムが極端に短い場合、制度の趣旨に反すると見なされる恐れがあります。
あくまで労働者の自主的な決定に委ねられていることが大前提のため、上司が日々の出退勤を指示するような運用も認められません。
フレックスタイム制でありがちな誤解と正しい運用方法

「フレックスタイム制」と聞くと、「好きな時間に働ける」「残業がなくなる」といったイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、これらはしばしば誤解を生む原因となります。
特にありがちな誤解は「出勤時刻は自由だけど、毎日8時間は働かないといけない」というケースです。これは、フレックスタイム制と時差出勤が混同されています。
フレックスタイム制では、1ヶ月などの「清算期間」内で定められた「総労働時間」を満たしていれば、日々の労働時間は労働者自身が自由に調整できます。例えば、ある日は5時間勤務で早めに帰宅し、別の日に多く働くことで帳尻を合わせるといった柔軟な働き方が可能です。
こうした誤解を放置したまま運用してしまうと、かえって長時間労働を招くなど、思わぬトラブルの原因にもなりかねません。
フレックス勤務は本当に早く帰れるのか?残業の仕組みを解説
「フレックス勤務だから、好きなときに早く帰れるんでしょ?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。結論から言うと「日によっては早く帰れるが、その分どこかで調整が必要」というのが答えです。
フレックスタイム制における残業は、1日8時間を超えたかどうかではなく「清算期間」という単位で計算されます。これは通常1ヶ月(最長3ヶ月)で設定され、この期間内の総労働時間(例えば160時間)を超えて働いた分が残業扱いになるのです。
そのため、ある日に10時間働いても、別の日に6時間勤務にするなど調整し、期間の合計が160時間以内に収まれば残業代は発生しません。逆に合計が170時間になれば10時間分が残業となります。
毎日早く帰れるわけではなく、計画的な時間調整が前提にあることを理解しておきましょう。
フレックスタイム制のシフト表作成方法|実例とテンプレート

フレックスタイム制では、労働者自身が日々の始業・終業時間を決めます。そのため、従来の固定シフトのように会社が「何時に出社、何時に退社」と指示するようなシフト表は存在しません。
その代わりに、清算期間における総労働時間を満たすための「目安となる勤務時間」や、チームとして連携が必要な「コアタイム」を可視化するためのスケジュールを共有することが重要になります。
例えば、チームメンバーの出社予定時刻や、コアタイム中の在席状況を一目で把握できる共有カレンダーやスプレッドシートを活用するのが一般的です。効率的なシフト表作成のためには、まずチームの業務内容や特性に合わせたルールを設定しましょう。
例えば「週に最低一度は全員が揃う時間を設ける」「顧客対応はコアタイム中に集中させる」といった具体的な取り決めが、調整をスムーズに進めます。さらに、テンプレートを用意すれば、毎月の作成の手間も省け、制度のメリットを最大限に活かせるようになるでしょう。
朝礼・定例会を柔軟に組み込む時間設定の工夫
全員参加が必須の朝礼や定例会は、フレックスタイム制の難しいところです。最も効果的なのは、会議を「コアタイム」内に設定することでしょう。
コアタイムは全員が必ず出社しているべき時間帯のため、この時間に合わせて会議を設定すれば、参加率の低下を防げます。さらに一歩進んだ工夫として、会議のアジェンダを事前に共有し「情報共有のみのパート」と「議論が必要なパート」を分けるのも有効な手段です。
情報共有のみなら、録画や議事録で後から確認できるようにすれば、参加を必須にしなくても問題ありません。このように会議の目的を明確化し、参加形式に柔軟性を持たせれば、フレックスタイムの自由度とチームの連携を両立させられます。
Excelで勤怠管理する場合のテンプレート活用法
手軽に始められる勤怠管理として、多くの中小企業で活用されているのがExcelです。テンプレートを使えば、専門的な知識がなくても比較的簡単にフレックスタイム制に対応した管理表を作成できます。
関数を組み込めば、始業・終業時刻を入力するだけで、その日の実働時間や月の総労働時間、残業時間まで自動で計算させることも可能です。ただし、手入力によるミスや打刻忘れの確認、法改正への対応など、手作業ならではのデメリットも存在します。
当サイトでは、すぐに使えるExcelテンプレートもご用意しておりますので、まずは一度試してみてはいかがでしょうか。規模が大きくなってきたら、勤怠管理システムの導入を検討してみても良いかもしれません。
関連記事:【テンプレート無料提供】エクセルで作るシフト表、タイムスケジュール表のコツを紹介!
フレックスタイム制とシフト勤務の併用は可能?成功事例も紹介

「個人の自由」を重んじるフレックスタイム制と、「会社の要請」で時間を組むシフト勤務。一見すると正反対の制度ですが、実はこの2つを併用したハイブリッドな運用は可能です。
この手法は、特に顧客対応などで「事業として最低限稼働させたい時間」と「従業員の柔軟な働き方」を両立させたい場合に、非常に有効な手段となります。例えば、店舗運営などがその代表例です。
大まかなシフトで人員が手薄になる時間帯を防ぎつつ、その枠組みの中では個人の裁量で出退勤を調整できる、といった形が考えられます。成功のポイントは、どこまでを会社のルールとし、どこからを個人の裁量に任せるか、その線引きを明確にすることです。
フレックスタイム制なのにシフト勤務を導入する理由
フレックスタイム制を導入している企業が、なぜあえてシフト勤務も併用するのでしょうか。そこには明確な理由があります。
理由は、事業運営上の必要性と従業員の働きやすさを両立させるためです。例えば、常に一定数の人員が必要な部署で完全なフレックスタイムを導入すると、偶然にも午前中に誰も出社しないといった事態が起こりかねません。
これでは、お客様への対応や業務の連携に支障が出てしまいます。そこで大枠のシフトを組むことで、会社は「最低限の稼働」を担保するのです。
従業員にとっても、決められたシフト内でなら柔軟に働けるという、固定シフト勤務にはないメリットが生まれます。ただし、制度が複雑化し管理が難しくなるというデメリットもあるため、導入には慎重な検討が必要です。
関連記事:アルバイトのシフト管理は大変なのです!シフト管理システムのメリット、特徴について教えます!
フレックスタイム制が普及しない理由とその解決策

柔軟な働き方を実現できるフレックスタイム制ですが、日本ではまだ全面的に普及しているとは言えません。
厚生労働省の調査によると、フレックスタイム制を導入している企業は2024年時点で7.2%にとどまっており、働き方改革が進む中でも、浸透にはまだ時間がかかりそうです。
普及を妨げている具体的な4つの理由と、その解決策について掘り下げていきましょう。
引用元:厚生労働省|令和6年就労条件総合調査の概況
制度運用の複雑さと管理負担
フレックスタイム制の導入や運用が、思った以上に複雑であることが普及を妨げる原因のひとつです。導入時には、就業規則への規定と労使協定の締結が法律で定められており、こうした手続きが最初のハードルとなります。
さらに日々の運用では、従業員一人ひとりの労働時間が異なるため、勤怠管理が煩雑になりがちです。特に「清算期間」における総労働時間の集計や、超過した分の残業代計算は、従来の管理方法に比べて手間がかかります。
この管理負担の増加が、特に人事・労務担当者のリソースが限られている中小企業にとって、導入をためらわせる大きな理由になっているのです。
業種・職種による適用制限
すべての仕事がフレックスタイム制に適しているわけではない、という現実も普及を妨げる要因となっています。例えば、店舗での接客業や工場の生産ライン、コールセンター業務などは決まった時間に複数人が協力して働く必要がある職種です。
このような業種では、従業員がバラバラの時間に出社すると業務が成り立ちません。また、社外の顧客とのアポイントメントが多い営業職なども、相手先の都合に合わせる必要があるため、制度のメリットを活かしきれない場合があります。
このように、業務の特性上、どうしても勤務時間を固定せざるを得ない業種・職種が存在するため、社会全体での普及率がなかなか進まないのです。
社内文化やマネジメントの慣習
制度を導入しても、それを活かすための社内文化が伴わないケースも少なくありません。特に日本では「長く会社にいる人ほど評価される」といった時間主義的な考え方が根強く残っている場合があります。
このような環境では、制度上は早く帰ることができても、上司や同僚の目を気にしてしまい、結局、形骸化してしまうのです。また、管理職が部下の働きぶりを直接見ていないと不安に感じたり、そもそも制度への理解が浅かったりすることも、円滑な運用を妨げます。
フレックスタイム制を成功させるには、ルールを作るとともに「時間」ではなく「成果」で評価する文化への変革と、管理職の意識改革が不可欠です。
従業員の制度理解不足と不公平感
従業員側の制度に対する理解不足や、運用から生じる不公平感も、普及の壁となっています。「フレックスタイム=残業しなくていい」といった誤った認識や、総労働時間を満たすための自己管理がうまくできず、かえって働きづらさを感じてしまうケースも少なくありません。
また、営業部など外回りの多い部署は制度を活用しやすい一方で、電話や来客対応が必要な内勤の部署では活用しにくいなど、配属される部署によって有利・不利が生まれてしまう不公平感も課題です。
こうした不満は、従業員のモチベーション低下に直結しかねません。導入時には、全従業員に対して説明会を開き、特定の部署だけが不利益を被らないような運用ルールを設ける配慮が必要です。
フレックスタイム制導入の成功事例|柔軟な働き方を実現する方法

フレックスタイム制の導入に成功している企業は、単に制度を取り入れるだけでなく、自社の文化に合わせて運用を工夫しているのが共通点です。
例えば、アサヒビール株式会社では、育児や介護と仕事の両立を支援するため、コアタイムを含む通常のフレックスタイム制に加え、コアタイムのない「スーパーフレックス制」まで導入しています。
制度導入によって、無駄な労働時間を削減し、在宅勤務やビデオ会議も活用し、生産性を維持しながら「プラチナくるみん」認定を受けるなど、高い実績を上げています。
また、三井物産ロジスティクス・パートナーズは、社員のオーバーワーク解消を目指し、フレックスタイム制の導入とともに、ライフ・クオリティの向上を積極的に働きかけました。その結果、従業員のワークライフバランスが改善されたことが、激しい競争のある業界で好業績を維持する要因にもなっているのです。
さらに、旭化成ホールディングスのように介護支援勤務制度とフレックスタイム制を組み合わせ、コアタイムの短縮や期間の定めを設けないことで、介護離職を防ぎ、優秀な社員の定着を実現している例もあります。
このように、形骸化させずに制度のメリットを最大限引き出すには、企業のミッションや従業員のニーズに合わせて、他の働き方支援策と組み合わせ、組織全体で取り組むことが重要です。
勤務シフト作成お助けマンで実現する効率的なシフト調整

特に、清算期間の計算、コアタイムとフレキシブルタイムの管理、そして何より従業員一人ひとりの希望を考慮したシフト調整は、手作業では非常に煩雑になりがちです。 「Excelのテンプレートだけでは限界がある」「もっと効率的に管理したい」と感じている担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこでご紹介したいのが、勤務シフト作成お助けマンです。 このシステムを使えば、フレックスタイム制における複雑なシフト調整を、簡単かつスムーズに行えます。
このシステムひとつで、従業員からの希望シフト収集から、労働基準法に準拠した自動計算、さらにはチームの業務特性に合わせた人員配置まで完結させることが可能です。
導入すれば、これまで手作業で膨大な時間を費やしていたシフト作成の時間を大幅に短縮し、管理担当者の負担を大きく軽減できるでしょう。 さらに、従業員も自分の勤務状況をリアルタイムで確認できるため、制度への理解が深まり、不公平感の解消にもつながります。
フレックスタイム制のメリットを最大限に引き出し、従業員と企業双方にとって最適な働き方を実現するために、ぜひ「勤務シフト作成お助けマン」の導入をご検討ください。