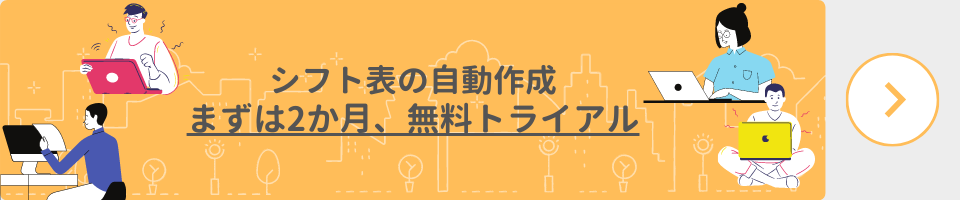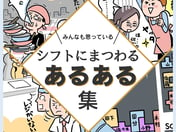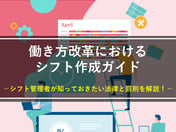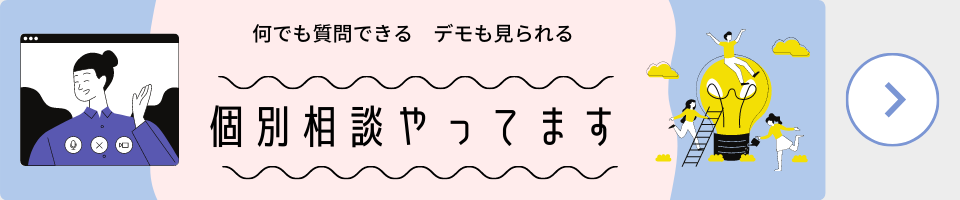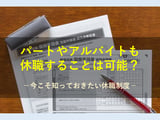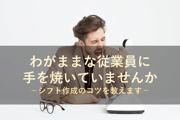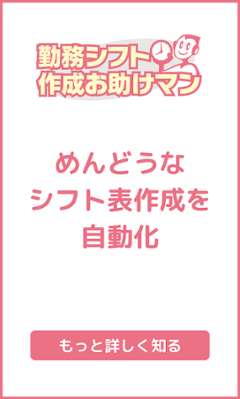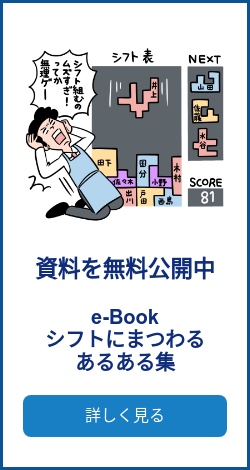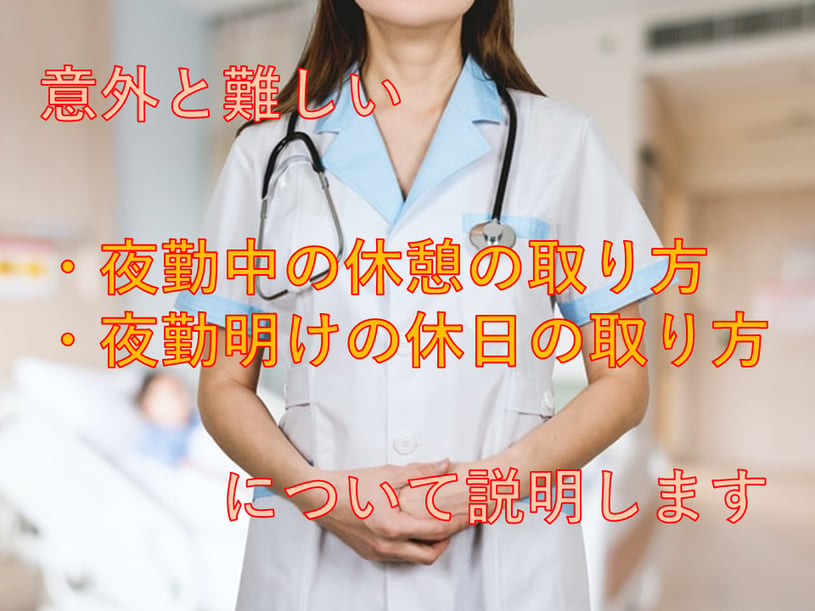
夜勤明けの次の日に、日勤を入れても問題はないのかといった疑問は、夜勤のある職場で働く人だけでなく、シフトを作成する管理者にとっても非常に重要です。
「夜勤明け→翌日日勤」というシフトが組まれることは少なくありませんが、法律上の扱いや健康リスクを正しく理解していないと、知らないうちに違法勤務や過重労働につながる恐れがあります。この記事では、夜勤明けの次の日に日勤を入れた場合の是非について、労働基準法や勤務間インターバル制度の観点から詳しく解説します。安全で効率的なシフト表を作成するためのポイントを確認していきましょう。
この記事でわかること
- ・「夜勤明けの翌日に日勤」は違法ではないこと。 労働基準法では労働日を暦日(0時〜24時)で判断するため、夜勤明けの日と翌日の日勤は別日の勤務と扱われ、直ちに法律違反にはならない。
- ・ 勤務終了から次の勤務開始まで11時間以上空ける「勤務間インターバル制度」が重要であること
- ・夜勤シフトで守るべき労働基準法の基本ルール
- 夜勤とは?
- 夜勤明けの次の日に日勤は法律上できる?できない?
- 夜勤入り・夜勤明け・明けとは?シフト用語をわかりやすく解説
- 夜勤明け → 日勤は違法?勤務間インターバル制度の基礎知識
- 夜勤明けにそのまま日勤・翌日日勤・翌日夜勤は可能?【パターン別】
- 法律で定める夜勤シフトのルール|労働基準法32条・35条
- 夜勤シフトの例|日勤→夜勤→明け→休みのサンプルを紹介
- 夜勤明けに必要な休憩・休日|健康リスクと注意点
- 夜勤シフトを安全に組むポイント|管理者が守るべき基準
- まとめ|夜勤明けの勤務は法律と健康を優先して判断を
夜勤とは?

夜勤とは深夜の時間帯に働くことです。一般的には夜から翌朝まで働くことを指し、夜勤を行う主な職種としては、看護や介護、24時間営業のコンビニエンスストアや、24時間稼働する工場などがあげられます。労働基準法では、深夜の時間帯とは午後10時~翌日の午前5時の間を指しており、この時間帯に勤務した場合は、通常の賃金に25%上乗せした賃金を支払います。
夜勤を行う職種の多くは、日中に働く「日勤」と夜勤を組み合わせたシフトにすることが一般的であり、夜勤のみを行う働き方は全体的には少なめといえます。
次の項目では、夜勤を行う職場でみられる「交代制」について説明します。
夜勤は主に「二交代」と「三交代」
夜勤は主に「二交代」と「三交代」に分けられます。
二交代の働き方は、日中に働く「日勤」と夜間に働く「夜勤」の二種類です。二交代の場合、日勤が8時間程度、夜勤が16時間程度の勤務となったり、日勤と夜勤がそれぞれ12時間勤務となったりすることもあります。二交代制の特徴は、夜勤の勤務時間が長くなることです。多くの場合、夜勤では仮眠の時間を確保するなどして、休憩を長めに取るようにしています。
三交代では、日中に働く「日勤」、夕方から深夜にかけて働く「準夜勤」、深夜から朝方にかけて働く「夜勤」の三つがあります。三交代制の場合、いずれも勤務時間はそれぞれ8時間となります。三交代は、二交代のように長時間のシフトとはならない反面、シフトのパターンが3種類あるため生活リズムが崩れやすくなりがちです。
▼あわせて読みたい記事
交代制勤務の働き方、シフト管理。2交代制、3交代制などの交代勤務のシフトを徹底解説します
夜勤明けの次の日に日勤は法律上できる?できない?

結論から述べると、夜勤明けの次の日に日勤のシフトを入れても法律上は「可能」であり、違法ではありません。
労働基準法において、労働日は原則として「午前0時から午後12時までの暦日」単位で判断されます。夜勤が日曜日の夜から月曜日の早朝にかけて行われた場合、それは「日曜日の業務」の延長として扱われ、その後に始まる月曜日の日勤は「月曜日の業務」という別個の労働日扱いになります。
例えば、月曜日の午前5時に夜勤が終了し、4時間後の午前9時から日勤が始まるような極端なケースであっても、出勤日が別々として扱われ直ちに法律違反となるわけではありません。
しかし、労働時間の上限、週1日の法定休日、そして近年重視されている勤務間インターバルの考え方を踏まえると、安易に夜勤明け翌日に日勤を入れるべきではないケースが多いのが現実です。
夜勤入り・夜勤明け・明けとは?シフト用語をわかりやすく解説

夜勤を含むシフト管理で押さえておきたいのが、「夜勤入り」「夜勤明け」「明け」という用語の意味です。まずはこれらの定義を整理しましょう。
夜勤入りとは、夜勤を開始する日を指します。たとえば18時からの勤務であれば、この時間が夜勤入りです。法律上は午後10時から午前5時までを「深夜勤務」と定義しており、通常の賃金に25%以上を上乗せした「深夜割増賃金」の支払い義務が発生します。
夜勤明けは、夜勤が終了する日のことです。例えば月曜の夜から火曜の朝まで働いた場合、火曜日の朝に仕事が終わった時点が「夜勤明け」となります。
「明け」とは現場用語で、「夜勤明け=明け日」と表現されるのが一般的です。この明け日を休みにするのか、半日勤務扱いにするのかがシフト上のポイントになります。
多くの人が誤解しがちなのは、「夜勤明け=休み」という点です。労働基準法には「夜勤明けは必ず休日に」とする条文はありません。
休日は原則として「0時から24時まで丸1日」労働義務がない日を指し、朝まで働いた「明け」の後は休みであっても休日にはカウントされません。
夜勤明け → 日勤は違法?勤務間インターバル制度の基礎知識

法律で禁止されていないとはいえ、夜勤明けから数時間で次の勤務に入るようなシフトは、従業員の健康を著しく損なう恐れがあります。
そこで近年注目されているのが「勤務間インターバル制度」です。この制度は、前日の勤務終了から次の勤務開始までに一定時間の休息を確保するという考え方です。
現時点では努力義務ですが、長時間労働や過労を防ぐ基準として、多くの医療・介護現場などで導入が進んでいます。夜勤明けにすぐ日勤を入れると、このインターバルが極端に短くなり、実質的に連続勤務と同じ状態になるため健康面・安全面で大きな問題が生じるからです。
インターバルは何時間必要?【原則11時間】例で解説
国は、健康確保の観点から「11時間以上」のインターバル確保を推奨しています。
たとえば、朝9時に夜勤が終了した場合、11時間のインターバルを確保すると次の勤務開始は早くても当日の20時以降です。
もし夜勤が午前8時に終わり、日勤が午後1時から始まる場合、インターバルはわずか5時間しかありません。このようなシフトは、努力義務に反する可能性があるだけでなく、従業員の安全配慮義務に抵触するリスクが高まります。
単純な時間計算だけではなく、夜勤という疲れやすい特殊性を考慮し、労働者の負担が大きくならないようにすることが大切です。
夜勤明けにそのまま日勤・翌日日勤・翌日夜勤は可能?【パターン別】

夜勤明けの後は、どのタイミングで次の勤務を入れればよいでしょうか。夜勤後の勤務パターンについて見ていきましょう。
パターン① 夜勤明け当日に日勤 → 基本NG
夜勤が朝に終了し、同日の朝からそのまま日勤に入るパターンです。法律上、出勤日が異なれば可能ですが、実務上は休息が全く取れず極めて危険なシフトといえます。
過労による事故や健康被害のリスクが非常に高く、企業の「安全配慮義務」違反に問われる可能性もあるでしょう。
パターン② 夜勤明け翌日日勤 → 労働時間次第でOK
夜勤が明けた当日は休み(明け休み)とし、その翌日から日勤に入る最も一般的なパターンです。これは法律上問題ありませんが、週40時間の法定労働時間を超えていないか、また十分な睡眠が取れているかを確認する必要があります。
パターン③ 夜勤明け翌日夜勤 → 適切な休息が必須
夜勤明けの翌日に再び夜勤に入る、いわゆる「夜勤の連続」です。法律上、連続夜勤の日数に直接の制限はありませんが、法定休日(週1日または4週4日)を確保できていなければ違法となります。
看護業界のガイドラインなどでは、連続夜勤は原則2回までが目安とされています。
法律で定める夜勤シフトのルール|労働基準法32条・35条

夜勤シフトを作成する管理者が、必ず守らなければならない法律の原則は以下の通りです。
労働時間上限(1日8時間・週40時間)
労働基準法第32条により、労働時間の上限は原則「1日8時間・1週40時間」と定められています。
夜勤であってもこの上限は適用され、これを超える場合には労使間の合意による労働基準監督署への「36協定」の届け出が必須です。36協定がない状態で残業をさせると違反となり、罰則の対象となります。
法定休日(週1日)と夜勤の扱い
第35条により、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
先述の通り、夜勤明けの日は「休日」ではないため、管理者は「明け休み」とは別に丸1日(0時〜24時)休みとなる法定休日を確保するようシフトを組む必要があります。
▼あわせて読みたい記事
【2026年版】シフトと労働基準法|違法にならないシフト作成のルールを専門家が解説
夜勤シフトの例|日勤→夜勤→明け→休みのサンプルを紹介

安全なシフトを組むには、無理のないローテーションが鍵となります。実務でよく見られるのが、日勤から夜勤に入り、夜勤明けを経て休みに入るシフトです。
この形はインターバルと休日を確保しやすく、比較的安全な組み方といえます。
看護・介護業界でよくある夜勤シフト例
看護・介護業界では「2交代制」か「3交代制」のシフトが採用されるのが一般的です。
2交代制の場合は、日勤と夜勤の2つに区分され、1回の夜勤は16時間と長時間になりますが、「明け休み+公休」などまとまった休みを取りやすいというメリットがあります。
一方で3交代制は日勤・準夜勤・深夜勤の3つに分けられており、準夜勤は夕方から夜にかけての勤務を指します。1回当たりの拘束時間は8時間程度になり、2交代制よりも労働時間が短くなりますが、シフトが細かく変動するため生活リズムを整えるのが難しくなるというデメリットがあります。
夜勤明けに必要な休憩・休日|健康リスクと注意点

夜勤を軽視すると、従業員は疲労が蓄積され深刻な健康被害をもたらすことがあります。
夜勤の健康リスク(睡眠不足・体内時計の乱れ)
産業医科大学医学部の研究では、夜間に光を浴び続けると、抗酸化作用のあるメラトニンの分泌が抑制され、がん(乳がんや前立腺がん)の発症リスクが高まると報告しています。
また、総コレステロールの上昇によるメタボリック症候群や、交代勤務睡眠障害(SWD)のリスクも指摘されています。
勤務間インターバルを確保する重要性
夜勤は体内時計を乱しやすく、睡眠障害や生活習慣病のリスクを高めます。
十分なインターバルがないと、疲労が蓄積しヒューマンエラーによる事故や病気の原因となります。特に医療や介護、運輸などの現場では重要な視点です。シフト管理者は、「法的にOKか」だけでなく、「従業員が心身ともに回復できるか」を最優先に考えるべきです。
夜勤シフトを安全に組むポイント|管理者が守るべき基準

安全で健全な職場を維持するための、シフト作成のコツは以下の通りです。
夜勤者の連続勤務を避ける
法律上の連続勤務は最大12日まで可能(週1日の法定休日を確保する場合)ですが、健康面を考慮すると3〜5日を上限にしたシフトが推奨されます。
特に看護職は連続勤務日数は5日以内、夜勤回数に関しては3交代制で月8回以内にするなど、独自のガイドラインが設けられています。
人員配置の偏りをなくす方法
「特定のスタッフばかり夜勤が多い」と感じられる状況は、不公平感を生みやすく、離職やモチベーション低下の大きな要因になります。
まず重要なのは、夜勤を特定の人に固定せず、ローテーションを明確なルールとして定めることです。誰が見ても公平だと分かる仕組みを作れば、納得感のあるシフト運用につながります。
また深夜帯は人員が限られるため、新人だけで夜勤を任せるのではなく必ず経験豊富なスタッフを組み合わせ、能力のバランスを取ることが大切です。さらに、夜勤者は年2回の健康診断が義務付けられており、その結果を踏まえて体調面に配慮したシフトを組むようにすれば、安全で無理のない人員配置を実現できます。
▼あわせて読みたい記事
【全30選】シフトに困っている人に勧めたいシフト作成システム・アプリ
【AIでシフト表を自動作成】勤務表の自動作成を特長とするシフト管理ツール10選|プロが教える失敗しない選び方
【2026年最新】シフト管理とは?課題を解決する効率化の方法とおすすめツール17選
まとめ|夜勤明けの勤務は法律と健康を優先して判断を

夜勤明けの次の日に日勤を入れるシフトは、法律的には可能ですが、「できること」と「させてよいこと」は異なります。
適切な勤務間インターバルの確保、割増賃金の支払い、そして法定休日の厳守は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の法的リスクを回避するためにも必須です。夜勤は社会を支える重要な労働ですが、その持続可能性は管理者の配慮にかかっています。
AIツールなどを賢く活用し、「法律の遵守」と「従業員のウェルビーイング」が両立した、安全な勤務体系を設計していきましょう。
JRシステムが提供する「勤務シフト作成お助けマンDay」は、「夜勤」の翌日は「夜勤明け」のような勤務の並びに関する条件や、勤務間インターバルを考慮した条件を事前に設定し、それらの条件にあったシフト表を自動で作成するサービスです。勤務条件は他にも、連続勤務日数、スタッフ組み合わせ、勤務回数、必要人数など、多くの条件を登録することができます。
「お助けマン」では、本利用と同じ機能を2か月間無料でトライアルできます。夜勤に関するシフト作成にお困りの場合は、この機会に是非、お試しください。