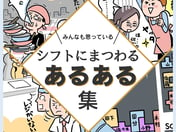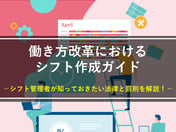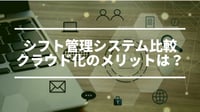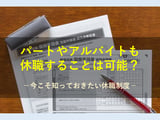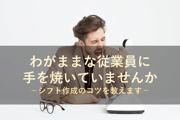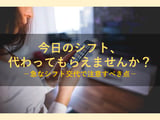隔日勤務がどのような働き方か気になっている方は多いのではないでしょうか。隔日勤務は勤務日数が少なくなるなどのメリットがある一方で、複雑なシフト管理が必要となる点が課題として挙げられます。
今回の記事では、トラック運転手やタクシードライバーを例に、隔日勤務の具体的な働き方について詳しく解説します。さらに、隔日勤務のメリットや課題も紹介していますので、隔日勤務の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
隔日勤務とは

隔日勤務の勤務パターンは、1日おきに勤務する形態です。その勤務時間について詳しく解説していきます。
1日おきに勤務する形態
隔日勤務は、1回の勤務が20時間以上続く勤務形態であり、その翌日は明け番として休みにする働き方です。例えば、朝8時に出勤し、途中で休憩を挟み、翌朝4時に勤務を終了するなどの働き方があります。
隔日勤務は、通常の労働基準法で定められている1日8時間の規定には合致しませんが、特例として認められている働き方です。一部の職種や産業で、連続して勤務する必要性があり、職種ごとに勤務時間が細かく定められています。
隔日勤務は、拘束時間が長くなりがちなドライバーなどの職種や、消防などの緊急性の高い職種でよく見られます。
隔日勤務を取り入れている職種
隔日勤務を採用している主な職種は以下の4つです。
・トラック運転手
・タクシードライバー
・消防士
・鉄道
これらの職種について、それぞれ詳しく説明していきます。
トラック運転手
トラック運転手の隔日勤務は、長距離運転者の安全と健康を考慮して組まれています。2日間の拘束時間は通常21時間以内に制限され、夜間に仮眠施設で4時間以上の仮眠を取れる場合は、2週間に3回まで、最大で24時間まで延長可能です。
また、2週間の拘束時間は合計で126時間を超えないよう制限されています。これは運転者の疲労を管理し、安全な運転を確保するためにも必要な措置です。フェリーに乗船している時間は休憩時間として扱われます。
長距離運転が必要なトラックドライバーは、安全のためにもしっかりと休息時間を取ることが重要です。
タクシードライバー
タクシードライバーの隔日勤務は、1カ月に通常11回の乗務が許されており、最大で13回までとされています。1回の乗務における拘束時間は通常15時間程度で、この時間内で乗客を運送し、車両のメンテナンスや休憩を取ります。
隔日勤務の特徴として、乗務後の休みの翌日から3連休となるケースがあることが挙げられるでしょう。連続して働く代わりに、次の3日間は休息を充分に取れます。
隔日勤務では、2日分の業務を1日にまとめて行うイメージです。乗務日は仕事が詰まっている一方で、休みの日はしっかりとリフレッシュを図れます。
消防士
消防士の隔日勤務は、一般的に2部制と3部制に分かれています。2部制では、隔日勤務を数回繰り返した後に3連休が設けられる勤務です。一方、3部制では、隔日勤務の後に1日の休みが入ります。
どちらの勤務体系を採用するかを決めるのは、自治体や消防署の方針です。地域や人員の状況、消防活動の需要などを考慮して、最適な勤務体系が採用されます。消防士は安全かつ効率的に勤務し、市民の安全を確保する役割を果たさなければなりません。
消防士の隔日勤務は、厳しい環境下での勤務を必要とする職業であり、適切な休息が不可欠です。
鉄道
鉄道の隔日勤務は、通常、朝9時から翌日9時までの勤務となります。勤務中には昼時間と夕方の時間にそれぞれ食事休憩が設けられています。さらに、15時頃に休憩があり、23時頃には仮眠休憩が設けられています。
15時頃の休憩は、日中の長時間勤務後に疲労を軽減するために設けられています。この休憩時間を利用して、体を休め、夜間の業務に備える必要があります。23時頃の仮眠休憩は、朝方の勤務に備えて一時的な休息を取るためにあります。
4時30分頃には仮眠から起床し、朝のラッシュに向けた業務を行い、勤務を終了します。
勤務時間と休憩時間
隔日勤務の勤務時間と休憩時間は、厚生労働省の改善基準告示によって定められています。労働基準法として問題がないことと、休憩時間の考え方を解説します。
労働基準法としては問題なし
厚生労働省は、トラック・バスとタクシードライバーの長時間労働を防ぐために、隔日勤務に関する基準を示した改善基準告示を職種ごとに定めています。
令和4年の見直しにより、勤務時間や休憩時間などの基準が改善されました。見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されています。
具体的には、トラックに関する改善基準告示の変更点は以下の通りです。
|
内容 |
改善前 |
改定後 |
|---|---|---|
|
1年の拘束時間 |
3,516時間 |
3,300時間 |
|
1カ月の拘束時間 |
293時間(最大320時間) |
284時間(最大310時間) |
|
1日の休憩時間 |
継続8時間 |
継続11時間(下限9時間) |
隔日勤務が労働基準法に適合する範囲内で行われるため、労働者の健康と安全が確保されるとともに、長時間労働の問題に対処するための適切な措置が取られることになります。
休憩時間の取り方
タクシードライバーの勤務時間として、拘束時間と休息時間の概念があります。拘束時間は、労働時間と休憩時間を含んだ時間であり、改善基準告示によって21時間以内と規定されました。
休息時間は、労働時間内の休憩時間とは異なり、勤務終了後に継続して必要な時間です。タクシードライバーにとっては、長時間の運転や交通渋滞などで疲労が蓄積するため、充分な休息が欠かせません。
そのため、勤務後には20時間以上の連続した休息時間が求められます。
休息時間の確保は、ドライバーの健康と安全を保つために欠かせず、交通事故や疲労過多による労働災害のリスクを低減する重要な要因となります。
隔日勤務のメリット
隔日勤務のメリットとして次の2点が挙げられます。
・月で考えると勤務日数が少ない
・急な勤務日の変更が少ない
それぞれ詳しく説明していきます。
月で考えると勤務日数が少ない
隔日勤務のメリットの1つは、月単位での勤務日数が少ないことです。例えば、タクシードライバーの場合、1カ月の拘束時間が262時間以内と定められています。
1乗務の拘束時間が20時間と仮定すると、月間の勤務日数は13.1日です。実質的に月の半分以上が休みとなります。
通常、勤務日数が13日から15日程度になることが多く、従来の日勤と比べて少ないです。隔日勤務制度を採用することで、労働者はより多くの休息を得られるため、労働時間の適正化が促進されます。
急な勤務日の変更が少ない
隔日勤務では、1回あたりの拘束時間が長いこともあり、急な勤務日の変更が起こりにくい傾向があります。このため、労働者は休みのスケジュールを立てやすいことがメリットです。
例えば、隔日勤務明けに3連休となる場合もあり、実質的には4連休となることもあります。定期的に長期の休みが取れるため、労働者はリフレッシュやプライベートの時間を確保しやすくなるでしょう。
また、急な勤務日の変更が少ないことで、生活の予定を立てやすくなり、ストレスを軽減できる点もメリットです。
隔日勤務の課題
隔日勤務には課題もあります。不規則な勤務パターンによって健康面に影響があること、シフトが複雑化することが挙げられるでしょう。
これらの点について詳しく解説します。
社員の健康・生活リズムの管理
不規則な勤務パターンにより、社員の睡眠や食事、運動などの生活リズムが乱れやすくなることが課題として挙げられます。社員に対する健康管理が欠かせません。
企業は社員の健康状態を把握し、適切な支援を提供するために、日常的なコミュニケーションを重視する必要があるでしょう。
例えば、乗車前の点呼を通じて声の状態から社員の健康状態を監視する仕組みを導入するなど、会社側で社員の健康管理を行う取り組みが求められます。
また、定期的な健康診断や健康教育プログラムの実施、適切な休息時間の確保なども重要です。
上限労働時間が決められている場合も
タクシードライバーにおいては、日勤、夜勤、隔日勤務それぞれに時間の上限が決められています。
隔日勤務では、勤務後の休息時間も日勤とは別に設ける必要があります。そのため、シフト管理が複雑になります。
シフト作成には多くの労力と時間が必要であり、簡易的かつ効率的なシフト作成方法が求められます。効果的な手段の1つとして、勤務形態に合わせてカスタマイズしてシフトを自動で作成できるツールの導入が挙げられるでしょう。
ツールの導入により、シフト管理の負担を軽減し、適切なシフトの作成や労働時間の適正化が促進されます。
まとめ
今回の記事では、隔日勤務がどのような働き方か、取り入れている職種やメリットを解説しました。隔日勤務は、1回の勤務が20時間以上続く勤務形態であり、その翌日は休みにする働き方です。
拘束時間が長くなりがちなドライバーなどの職種や、消防などの緊急性の高い職種でよく見られます。
勤務時間と休憩時間は、厚生労働省の改善基準告示によって改定されました。1日の拘束時間や休息時間などが職種ごとに定められているため、法令を遵守したシフトとなるように管理しなければなりません。
勤務日数が少ないことなどのメリットがある一方で、シフト管理が複雑化するなどの課題もあります。勤務形態に合わせて自動でシフト作成ができるツールもあるため導入を検討してみるのもよいでしょう。