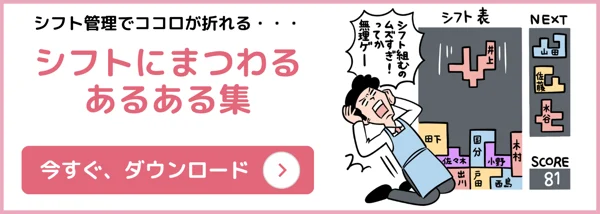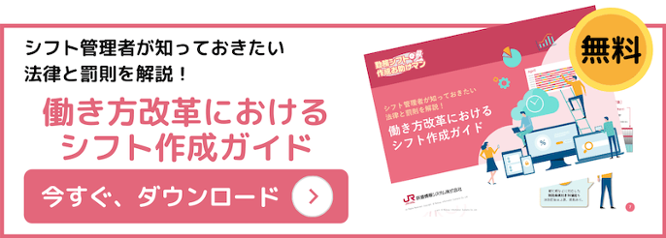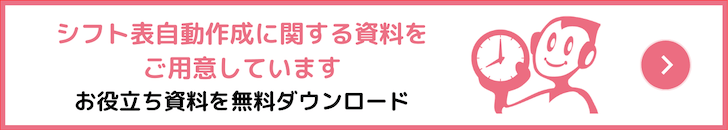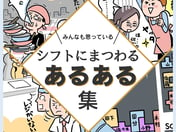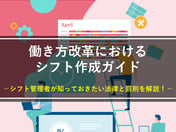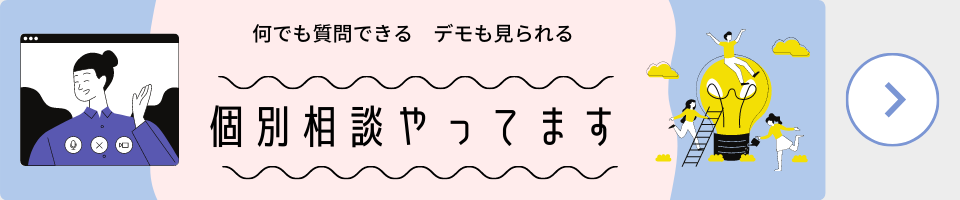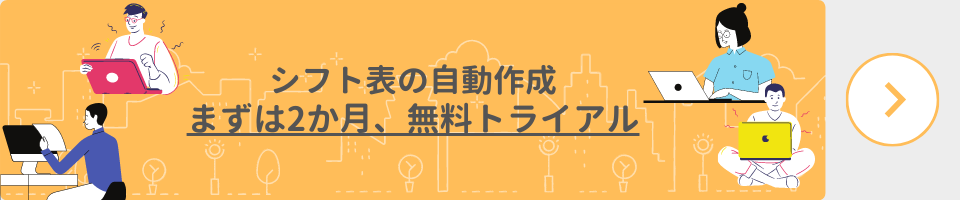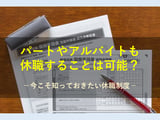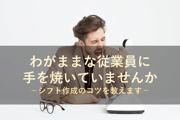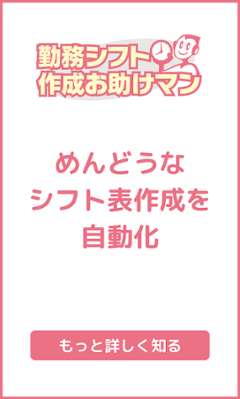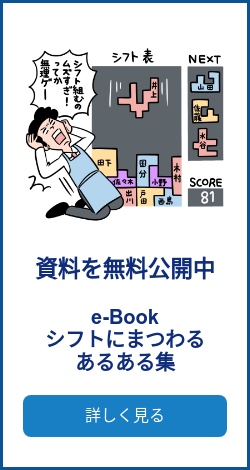2024年4月から時間外労働時間の上限が960時間に規制されたことにより、物流業界は多くの課題に直面しています。
今回は、新たな課題に適切に対応するために、2024年問題によってもたらされる具体的な変化、物流業界における影響、そしてこれら課題への対応戦略について深掘りしていきます。
物流の2024年問題とは
2024年4月1日から、働き方改革関連法の一環として、物流・運送業におけるドライバーの、年間時間外労働時間の上限が設定されました。
「2024年問題」とは、新たな労働時間規制に伴って生じると予想される、さまざまな問題を指します。トラックドライバーを取り巻く環境は、長年にわたり長時間労働が常態化していることが問題とされてきました。労働力不足やEC市場の拡大による宅配便の増加が、この状況をさらに悪化させています。新しい法改正の目的は、時間外労働の上限設定によるドライバーの負担軽減です。
このように聞くと、ドライバーの残業が減るのは好ましいことだと思えます。確かに今回の法規制による労働時間の短縮は、歓迎すべきことです。しかし、単純に労働時間を短縮すれば、全ての問題が解決するわけではありません。
法改正によって、ドライバー不足の深刻化、業務効率の低下や物流コストの増加、中小企業の経営圧迫などの課題が懸念されています。運送業者だけの努力では、2024年問題を解決することは困難です。荷主、運送業の事業者、一般消費者が一体となって物流環境を改善していくことが重要です。
物流の2024年問題で何が変わった?
注目される2024年問題ですが、これまでと何が変わるのでしょうか。4つの変更点を見ていきましょう。
時間外労働の上限が年960時間に
時間外労働の上限が年960時間に設定されました。これまでトラックドライバーに対する時間外労働の上限は存在しませんでしたが、2024年4月1日からは36協定を条件に、年間960時間という上限が適用されます。
拘束時間や休息時間、連続運転時間の基準
拘束時間や休息時間、連続運転時間の基準は次のように変更されます。
<1年間の拘束時間>
現行の3516時間から、原則3300時間へと短縮されます。労使協定を結べば、最大3400時間までの延長が可能です。
<1か月の拘束時間>
原則293時間から284時間へと変更され、310時間までの上限が設けられます。
<1日の拘束時間>
現行の原則13時間以内で変化はありません。しかし、最大拘束時間がこれまでの16時間以内から13時間以内へと短縮されます。また、14時間を超える労働は週に2回までです。
<休息時間>
現行の8時間から11時間へと延長され、下限は9時間です。
宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は1週に2回までとし、継続8時間以上の休息を設けることが定められています。さらに、休息期間が9時間以下の場合は、運行終了後に継続して12時間以上の休息が必要です。
<連続運転時間>
現行の4時間を超えないことと、休憩は1回約10分以上であれば分割が可能であることは変わりません。しかし、現行の“休憩等”から、“休憩”へと変更されます。
“休憩等”とは運転をしていない時間を意味し、荷物の積み下ろしや待機時間など運転以外の業務も含まれていました。施行後は、純粋な休憩を取ることが求められます。
1か月の労働時間
今回の法改正では、年間960時間の上限が設けられました。1か月平均に換算すると、80時間となります。
しかし、1か月の上限については規定がありません。1か月あたりの時間外労働が100時間を超えても、年間960時間以内であれば問題ありません。つまり、繁忙期などで一時的に残業時間が増えた場合でも、他の月で調整すれば大丈夫ということです。
時間外労働の割増賃金率
これまで、1か月あたり60時間を超える時間外労働に対する割増賃金は、大企業は50%増、中小企業は25%増とされていました。しかし、2024年4月1日からは、中小企業も月60時間超の時間外労働に対して、割増賃金率50%が適用されます。月60時間時間以内の時間外労働であれば、割増賃金率は25%です。 さらに22時から翌5時(条例によっては23時から翌6時)までの深夜時間帯における時間外労働では、深夜割増賃金として25%が加算されます。
これによって、60時間を超える時間外労働かつ深夜労働の場合の割増賃金率は、75%になります。なお、法定休日(週1日)の勤務では、割増賃金率は35%以上です。60時間超の残業が常態化している運送業者では、人件費が上昇する可能性があります。
物流業界が2024年問題に対応する方法とは
物流業界は人材不足と利益減少という2大課題に直面しています。運送・物流会社で働くドライバーの賃金は、基本給が他業種に比べて低いケースが多く、多くのドライバーが残業によって収入の上乗せを図ってきました。しかし、今回の法規制の変更によって、時間外手当の減少に伴う収入減が予想され、ドライバー職の魅力が低下するのではないかと危惧されています。これらの課題を克服するために、物流業界では「人材確保」と「労働状況の正確な把握」が重要です。
人材の確保
従来の長時間労働・低賃金という職場環境では、優秀な人材を確保するのは困難です。働き方改革を進め、「働きやすい環境」の整備が求められます。
具体的には、労働環境・労働条件の改善、柔軟なシフト体制の導入、福利厚生の充実などが考えられます。特にドライバーにとって、今回の法規制は収入減に直結する大きな問題です。給与制度の見直しや、各種手当・福利厚生の充実は急務といえるでしょう。長時間労働の課題を解決するためには、輸配送の仕組みそのものを見直すことも有効な手段です。
これまでのように、一人のドライバーが長距離輸送の全行程を担当する形態は、長時間労働の最大の原因です。以下の方法も検討しましょう。
- ・複数人体制によるリレー運送
- ・幹線輸送と集荷・配達の分担
- ・一部区間を鉄道や船舶にシフトする“モーダルシフト”導入
輸配送の仕組みを見直すだけでなく、柔軟なシフト体制の導入も急務です。
長時間労働・休日不足を解消するためには、固定的な勤務制度の見直しが必要です。フレックスタイムや時差出勤、短時間勤務など、勤務時間に柔軟性を持たせるシフト体制の採用や、有給休暇が取得しやすい環境を整えるための施策を検討しましょう。
柔軟なシフト体制の導入は、ドライバー個々の事情に合わせた働き方を可能にし、ワークライフバランスの向上や疲労軽減を実現します。その結果、人材確保・定着率向上、安全性の向上など、多くのメリットが得られるでしょう。
しかし、柔軟な働き方への対応には課題もあります。例えば、運送業の複雑なシフト管理では、必要な人材の調整が困難であること、深夜や早朝の出退勤も多いため勤怠状況が把握できない場合があるなどが挙げられます。
このような課題を解決するためには、シフト管理システムの導入が効果的です。トラックドライバーの複雑なシフト管理や柔軟な働き方に、自動で対応することができます。シフト管理にかかる時間の削減も可能ですし、法令遵守のもとで手間なく適切なシフト体制を作成できることが大きなメリットです。
労働状況を把握しやすい管理方法の採用
時間外労働の上限規制を遵守し、柔軟な働き方への対応を可能にするためには、ドライバーの労働状況を正確に把握する必要があります。運行計画の見直しも、ドライバーの労働時間削減に効果的です。コストを考慮しながら、高速道路の利用など空車時間短縮を目指しましょう。
これら勤怠管理や車両・運行管理を正確かつ効率的に行うためには、デジタルツールの導入が非常に有効です。たとえば、労働時間管理システムは、ドライバーの労働時間、休憩時間、残業時間などの管理が容易になるのがメリットです。
ドライブレコーダーによる運行管理では、車両管理業務の効率化やドライバーの作業効率の向上などに貢献するでしょう。デジタルツールやシステムを導入時する際は、機能や使いやすさを比較検討し、自社のニーズに合ったシステムを選ぶことが重要です。
また、従業員教育や研修を行い、システムを正しく利用できるようにする必要があります。そして、システムの運用ルールを明確化し、遵守することを社内に徹底させましょう。
まとめ
物流の2024年問題は、単なる法令遵守以上の課題であり、業界全体の意識改革と組織文化の変革が必要です。物流・運送会社の対応策としては、人材確保に加え、ドライバーの労働状況を把握しやすい管理方法の採用が不可欠です。
適切な対策を講じることで、ドライバーの健康と安全を守り、物流業界全体の効率と生産性を向上させることが可能です。業界全体の活性化のために、2024年問題をチャンスと捉え、新たな時代への適応を図りましょう。