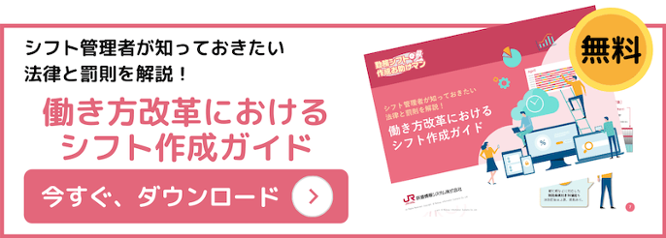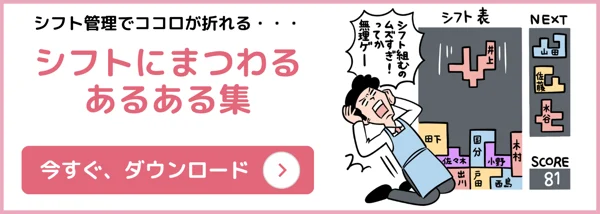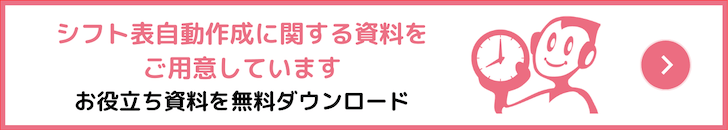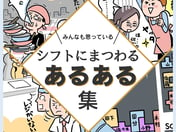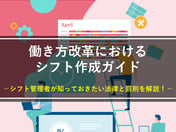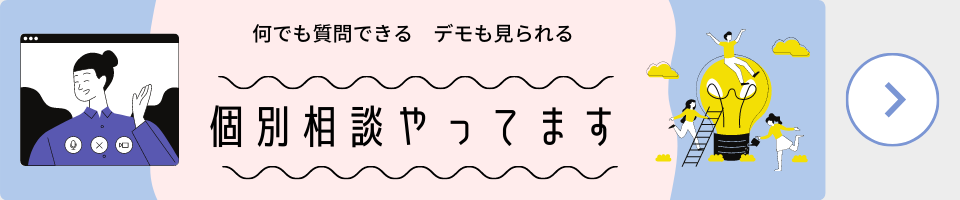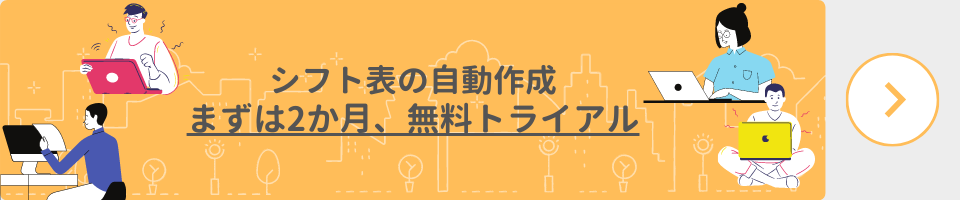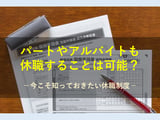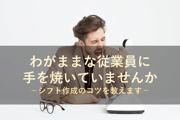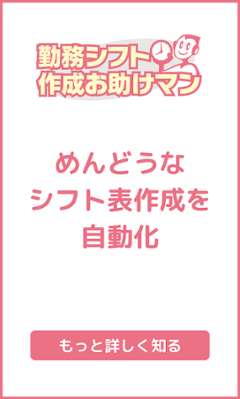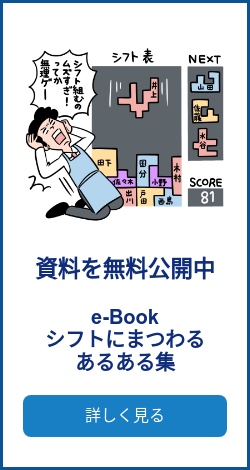業務の効率化や生産性の向上に取り組むには、所属するスタッフを適切に管理していくことが重要です。スタッフの管理をしっかりと行っていく1つの方法として、「マンアワー」(Man-Hour)があげられます。
業務のムダやムラを無くし、社内のリソースを最大限に活用していくために必要となる施策を実行していきましょう。また、マンアワーは店舗のシフトを組むうえでも有効であり、多店舗展開を行っている企業にはより効果的です。
今回は、マンアワーのとらえ方や活用方法について詳しく解説します。

マンアワーの定義
.jpeg?width=2000&name=man-hour%20(2).jpeg)
マンアワーを賢く活用するために、まずは言葉の定義をしっかりと押さえておく必要があります。ここでは、マンパワーとの違いも含めて見ていきましょう。
マンアワーは1人で作業を行ったときの時間を示す指標
「マンアワー」(Man-Hour)とは、特定の仕事を1人で行ったときの作業時間を示す単位のことを指します。日本語では「人時」(にんじ)とも呼びます。
1人で1時間かかる仕事量が「1人時」であり、5人で10時間かかれば「50人時」のように表すことで、作業を終わらせるためにどれくらいの時間や人数が必要であるかを示しています。マンアワーのとらえ方としては、スタッフの能力がほぼ等しく、投入する人数に正比例して仕事が速く進むことが前提となっています。
そのため、定型的な業務や単純作業には当てはめやすいものの、個人の能力差が激しかったり、作業の並列化が困難だったりする場合には適用が難しいといった特徴があります。
※作業時間を日単位で表した「人日」(にんにち)や、月単位で表した「人月」(にんげつ)、年単位で表した「人年」(にんねん)などの使われ方があります。
マンパワーとの違い
「マンパワー」は、人間の労働力そのものを指す言葉です。人手といった意味合いであり、実際に投入できる人的資源という性質を持ちます。
マンパワーが労働力や労働資源を表す言葉であるのに対して、マンアワーは仕事を終わらせるために必要な時間や人数のことを指しています。そのため、管理の面から見ればマンアワーによって捉えていくことが重要です。
▼あわせて読みたい記事
シフトに困っている人に勧めたいシフト管理システム・アプリ
自動作成を特長とするシフト管理システム|導入する前に知っておくべきこと
シフト作成に特化したシフト管理システム比較|クラウドのメリットとは
マンアワーを用いて管理を行う3つの指標
.jpeg?width=2000&name=man-hour%20(3).jpeg)
マンアワー(※以下、MHと略します)で管理を行う指標として、「必要MH」「投入MH」「過不足MH」の3つがあげられます。それぞれの指標について、どのような特徴があるのかを解説します。
必要な人員の合計時間を示す「必要MH」
「必要MH」は、業務を行う上で必要となる人員の合計時間数を示したものです。例えば、平日の必要MHは500MH、土日の必要MHは800MHといった使い方をします。
必要MHを計算する方法としては、個別の作業のMHを合算する方法もしくは、時間帯ごとに必要な人数を割り出して1日あたりの必要MHとする方法のいずれかがあります。
実際に投入できた人員の合計時間を示す「投入MH」
「投入MH」は、実際に作業へ投入できた人員の合計時間数を示したものです。例えば、平日の投入MHは300MH、土日の投入MHは500MHなどのように表します。
投入MHでは、実際に投入した人員の合計時間となるので、シンプルで分かりやすいのが特徴です。勤怠管理から投入MHを把握することができます。
現場の見える化につなげる「過不足MH」
「過不足MH」は、投入MHから必要MHを差し引いた数値となります。過不足MHを計算することで、曜日ごとや時間帯別のムダなどが明確になるといった特徴があります。
つまり、過不足MHによって作業全体の見える化につなげることができ、業務効率を改善していくポイントを明らかにできます。過不足MHを用いれば、現場の状況を的確に把握できるので、有効な改善策を打ち出しやすくなるでしょう。
マンアワー管理は多店舗展開に効果を発揮する
.jpeg?width=2000&name=man-hour%20(4).jpeg)
マンアワーを用いた管理手法は、各店舗の月別・日別・時間帯別の過不足をきちんと把握することに有効です。全店舗に導入すれば、店舗間のバラつきを細かくチェックできます。ここでは、マンアワーによる管理の効果について見ていきましょう。
他店舗との比較で業務を効率化してみよう
マンアワーによる管理は、月別・日別・時間帯別に分けて管理するのが一般的です。データを蓄積していけば、月間・年間での推移を比較することができます。
また、店舗別に比較してみることで問題のある店舗を発見しやすく、早期に改善策を講じることが可能となります。全店平均と比べることで、店舗ごとの位置づけをうまく把握できるでしょう。
しかし、店舗によって立地や規模が異なる面もあるため、ある程度のグループ分けを行うことが大切です。また、数値の羅列だけでは状況を把握しづらいので、グラフ表示などビジュアル面を工夫するとより効果を発揮できます。
生産性をアップさせるための基本的なポイント
マンアワーの視点でとらえる生産性とは、労働者1人が1時間働くことで得られる人時生産性となります。人時生産性は「粗利益高÷投入MH=生産性」で判断ができます。つまり、この計算式から分かることは、粗利益高を高めるか投入MHを減らせれば生産性が向上するという点です。
粗利益高を高めるには、数量管理や品質管理を向上させ、売上をアップさせることが重要です。また、投入MHを減らす方法としては、作業工数を減らしたりスタッフのスキルアップを図ったりすることがあげられます。
大切なことは、マンアワーの管理によって得られた数値をもとに、現場レベルの業務改善にまでつなげていく点です。単に数値だけを追ってしまうのではなく、どうすれば生産性を高められるかといった視点を持つようにしましょう。
マンアワー管理にはシフト作成の効率化が欠かせない
.jpeg?width=2000&name=man-hour%20(5).jpeg)
マンアワー管理においては、スタッフの人員配置が重要であり、円滑にシフトを作成することが必要です。クラウド型の自動作成ツールである「勤務シフト作成お助けマン」について、マンアワーの考え方をどのように生かせるのかを解説します。
人的なリソースをムダにしないことが重要
「勤務シフト作成お助けマン」では、各スタッフはスマホから勤務日や休みの希望を登録することが可能です。そのため、スタッフの希望を反映させながらも、勤務条件に沿った形でシフトを作成できます。
日単位に業務を割り当てる「お助けマンDay」と、時間単位に業務を割り当てる「お助けマンTime」があり、「お助けマンTime」では、マンアワーの考えに基づいた時間ごとの必要人数での入力が可能です。また、スタッフの希望や労働時間の上限、連続勤務日数や就業規則なども考慮した上で、最適な勤務時間や休みを割り出すことができます。
また、各店舗のシフト表を一元管理できるため、マンアワーの把握が簡単に行えます。小売業やサービス業など、多店舗展開している業種に向いているサービスです。
クラウド型のシフト管理ツールで業務負担を減らそう
「勤務シフト作成お助けマン」には、2ヶ月間の無料トライアル期間が設定されているので、実際に操作性や使い勝手を試してみてから導入を検討できます。シフト作成を担う管理者の意見やスタッフの声なども交えながら、自社に合ったシフト管理ツールであるかを確かめられます。
幅広い業種で導入されているツールであり、操作性に優れているので、初めて使う場合でも心配いりません。シフト作成の負担が減ったと感じたら、ぜひ本格的な導入を考えてみましょう。
まとめ
マンアワーは、作業を達成するのに必要な人員や時間数をきちんと把握するために重要な手法の1つです。組織のムダやムラを数値化することで、必要となるポイントに対して早期に改善策を打ち出せます。特に多店舗展開を行っている企業にとって、マンアワーでの管理は不可欠だと言えるでしょう。同時に、マンアワーを効果的に生かすためにはシフト管理も適切に行うことが大切です。シフト管理ツールをうまく活用して、シフト作成の手間を減らしつつ、適切な人員配置を行ってみましょう。