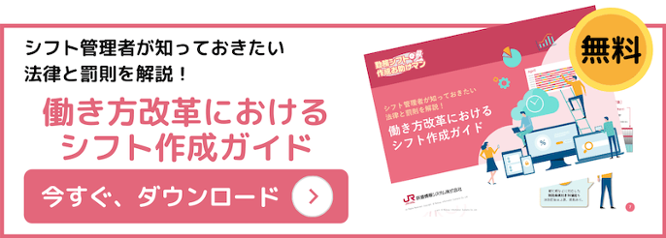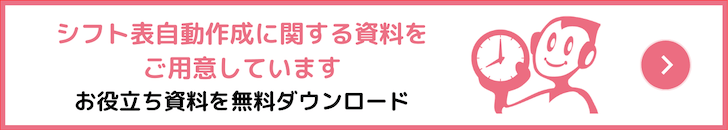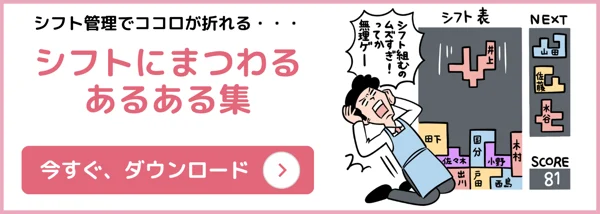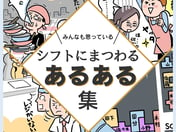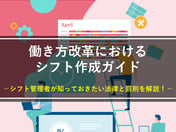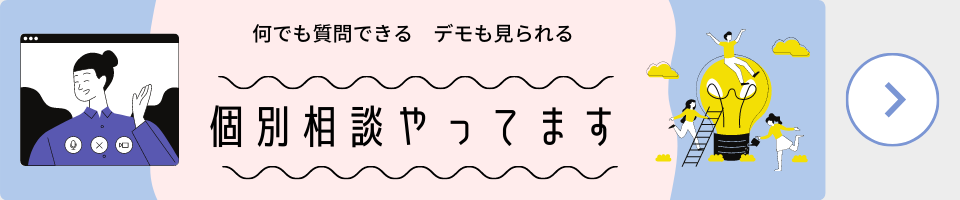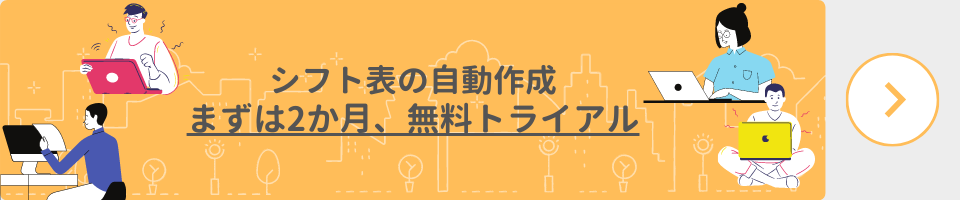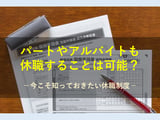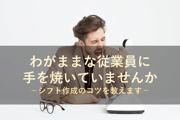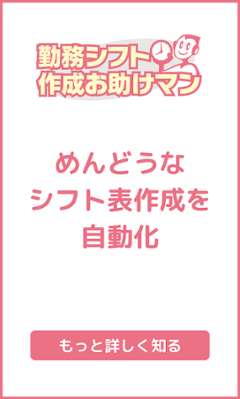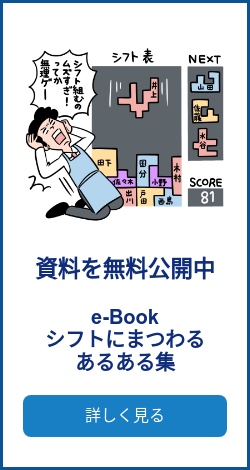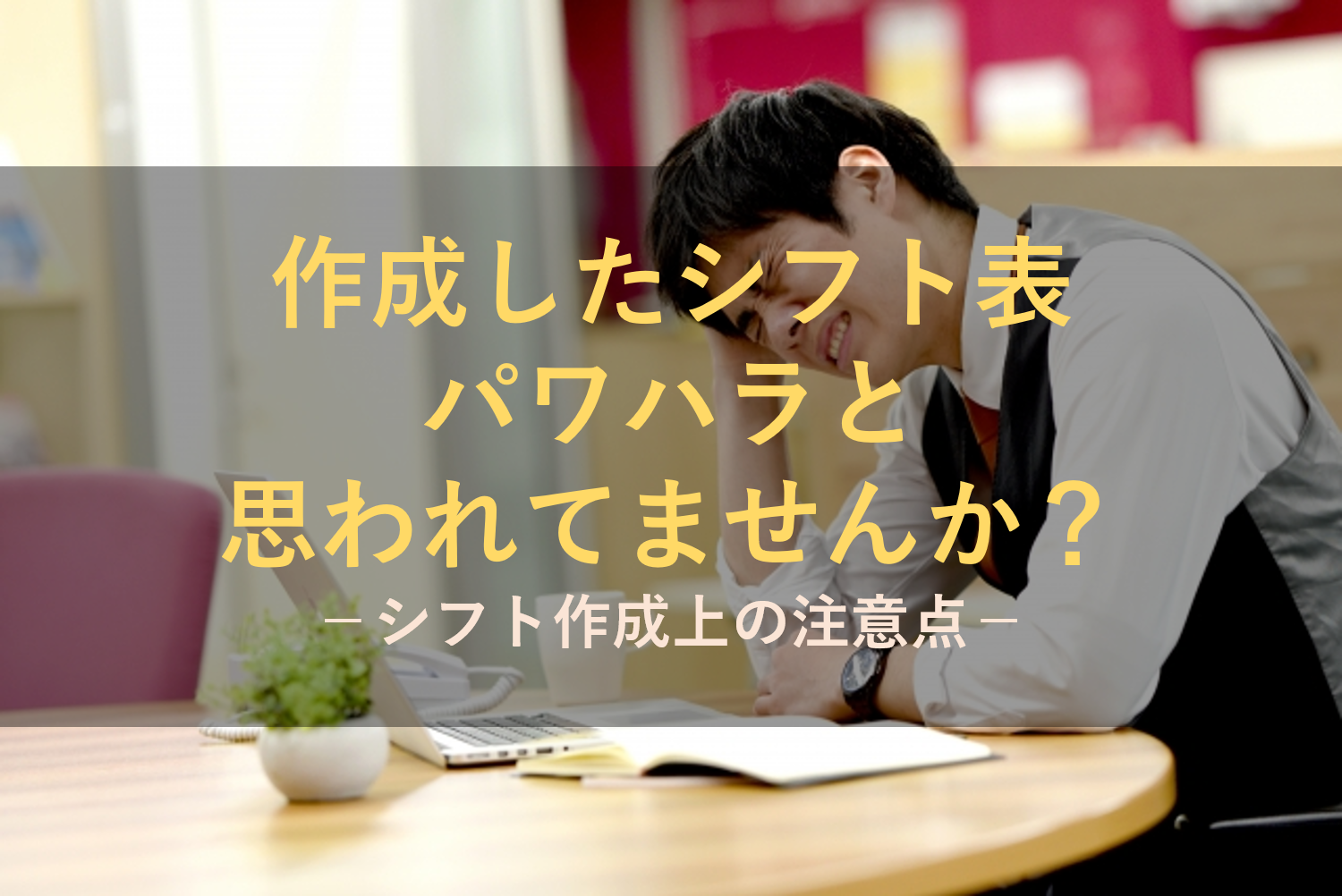 シフト作成者にとって、シフトの作成は手間がかかる作業です。本部から指示された人件費予算に基づいて、現場のオペレーションをスムーズに回すためにも、適切なシフトを作成しなければなりません。やっとの思いでできあがったシフトをスタッフに公表すると、スタッフの中にはパワハラと感じてしまう人がいる場合もあります。
シフト作成者にとって、シフトの作成は手間がかかる作業です。本部から指示された人件費予算に基づいて、現場のオペレーションをスムーズに回すためにも、適切なシフトを作成しなければなりません。やっとの思いでできあがったシフトをスタッフに公表すると、スタッフの中にはパワハラと感じてしまう人がいる場合もあります。
作成したシフトがパワハラと思われないために、シフトを作成するうえでの注意点について説明します。
- シフトの作成がパワハラととらえられる事例
- できあがったシフトがパワハラと思われないための対策は?
- パワハラと思われないシフトを作成するために意識したいことは?
- まとめ

シフトの作成がパワハラととらえられる事例
シフトを作成する側としては、その日の作業量や割り当てられる人員を加味しながらシフトを作成することでしょう。しかし、できあがったシフトをスタッフが見た場合、スタッフの中には「これではパワハラだ」と感じてしまう人もいます。
シフト作成に時間をかけたにもかかわらず「パワハラだ」といわれてしまうと、シフト作成者としては心外だと感じるのではないでしょうか。どんなシフトを作成すると「パワハラ」と感じてしまうのでしょうか。具体的な事例について説明します。
他のスタッフと比べて、シフトに入る日が多すぎる
他のスタッフと比べてシフトに入る日が多すぎると、スタッフの中にはパワハラに感じてしまう人もいます。
例えば、ほとんどのスタッフが週に3日しかシフトに入っていないのに対し、特定のスタッフだけ週に5日間シフトに入れたとしましょう。シフトの作成者は「1週間に3日間働く条件で採用した人は、週3日勤務とするが、1週間の勤務日数に条件を設けなかった人は、1週間に5日シフトに入れる」という考えを持っているとします。しかし、週5日シフトに入っているスタッフは、シフト作成者の考えがわからなければ「自分ばかり休日が少なく、労働を強要されている」と考えてしまいがちです。
特定のスタッフだけシフトに入れる日を増やしてしまうと、パワハラにとらえられる可能性がある点に注意しましょう。
他のスタッフと比べて、シフトに入る日が少なすぎる
逆に、他のスタッフと比べてシフトに入る日が少なすぎると、スタッフはパワハラに感じてしまう場合があります。
例えば、ほとんどのスタッフが週に3日シフトに入っているにもかかわらず、特定のスタッフだけ週に2日しかシフトに入れていなかったとしましょう。シフトを作成する立場としては、会社の売上がなんらかの事情で減ってしまった場合、売上の減少に応じて通常よりも人員を少なくすることがあります。しかし、特定のスタッフだけシフトに入る日が少なければ、そのスタッフは「なぜ、私だけシフトに入る日が少ないのだろう。もしかしてパワハラを受けている?」と考えてしまいかねません。
このように、特定のスタッフだけシフトに入る日が少なくなってしまうと、パワハラに感じてしまうことがあります。
夜勤など、負担の大きいシフトがメインになっている
夜勤など、負担の大きいシフトがメインになっているとパワハラに感じてしまう場合があります。
例えば、三交代制のシフト制が組まれている職場である場合、日勤と準夜勤、夜勤のシフトが組まれます。通常であれば、日勤と準夜勤、夜勤のシフトを交互に組み合わせることが基本となります。しかし、一部のスタッフが、諸事情によって日勤と準夜勤しかできないとしましょう。そのような場合、シフトの作成者は、特定のスタッフの日勤や準夜勤を少なくする反面、夜勤のシフトを増やす場合があります。
夜勤のシフトが多いスタッフに対し、シフトの作成者が夜勤を増やす理由を伝えていなければ、そのスタッフはパワハラを受けていると感じてしまうことでしょう。やむを得ず夜勤を増やす場合は、その理由をスタッフに伝えておく必要があります。
ワンオペのシフトとなっている
そのほか、いわゆる「ワンオペ」のシフトになっている場合は、パワハラを受けていると感じやすくなります。
ワンオペとは、コンビニや小規模な飲食店などで、深夜などの客数が少ない時間帯に限り一人の従業員で運営する方式のことです。経営者側としては、人件費を削減する観点からワンオペに踏み切ることがあります。しかし、ワンオペでしかも長時間労働となる場合、一人の従業員が店舗の業務の全てを行わなければならないため、非常に負担の強い働き方となります。
ワンオペを実施すると、サービスレベル低下につながるだけでなく、防犯上の観点から見ると防犯に不備がある方式といえます。よほどのことがない限り、ワンオペのシフトは組まない方が無難といえるでしょう。
▼あわせて読みたい記事
シフトに困っている人に勧めたいシフト管理システム・アプリ
自動作成を特長とするシフト管理システム|導入する前に知っておくべきこと
シフト作成に特化したシフト管理システム比較|クラウドのメリットとは
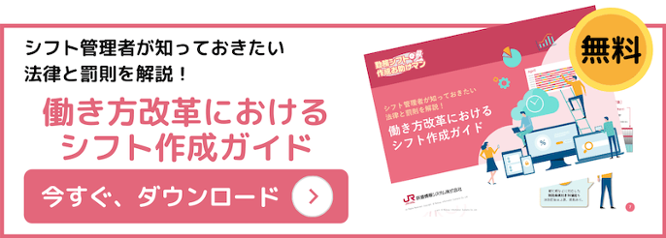
できあがったシフトがパワハラと思われないための対策は?

手間をかけて作成したシフトであっても、その内容によっては、スタッフからは「こればパワハラではないか」と受け止められてしまうことがあります。シフトの作成がパワハラに思われないための対策としては、下記があげられます。
- ・シフトを早めに作成する
- ・偏りのないシフト作成を心がける
- ・労働基準法が守られているシフトを作る
それぞれの内容について説明します。
シフトを早めに作成する
できあがったシフトを見て、スタッフからパワハラと受け止められないようにするには、シフトを早めに作成することがポイントとなります。
シフトを早めに作成した方が良い理由は、できあがったシフトを客観的な視点で見直すことができるためです。シフトを見直す時間があれば、特定のスタッフだけ出勤日が多くなったり、少なくなったりしていないか、スタッフがシフトに入る日は、平日と土日祝日が均等になっており、土日祝日の出勤に偏っていないか、という点をチェックできます。シフトを早めに作成しておけば、シフトに偏りがあることを見つけたら、手直しすることも可能です。もし、シフトの作成をギリギリの状態で行ってしまうと、シフトを見直す時間が取れないため、出勤日に偏りがあるシフトをそのまま使うことになってしまいます。
あらゆるトラブルを防ぐには余裕を持って行動することが大切です。それを踏まえると、シフトは早めに作成しておくことが重要といえます。
偏りのないシフト作成を心がける
シフトを作成する場合に気をつけたいことは、スタッフの出勤日や出勤時間帯に偏りがない状態にしておくことです。
特に、それぞれのスタッフの出勤日や出勤時間の合計はほぼ同じになっているか、という点をチェックしておきましょう。また、スタッフの出勤日や出勤日数がほぼ同じになっていても、特定のスタッフに限り、忙しい時間帯や曜日に多くシフトを入れてしまうケースもみられます。なぜなら、仕事ができるスタッフを忙しい時間帯や曜日にシフトを入れると、現場をスムーズに運営しやすくなるためです。しかし、そのようなシフトを作成してしまうと、スタッフが不公平と感じたり、パワハラと感じたりする原因につながりかねません。そのような状態を防ぐためにも、出勤日数や出勤する曜日、出勤する時間帯に偏りが生じないようにしましょう。
労働基準法が守られているシフトを作る
シフトを作成する場合に抑えておきたいことは、労働基準法が守られているシフトを作ることです。
例えば、労働基準法で守る必要がある内容として、残業時間の上限があります。政府は時間外労働の上限を、原則として月45時間、年360時間と定めています。ただし、月45時間の時間外労働が認められていても、それを毎月行えば、年360時間という時間外労働の上限をオーバーしてしまいます。そのため、年360時間という時間外労働の上限を超えないためには、1か月あたり30時間以内に抑える必要があります。
職場によっては、人手不足のため、やむを得ず残業が発生するシフトを作成しなければならないこともあるでしょう。しかし、労働基準法を守っていなければ、スタッフからパワハラと訴えられるだけでなく、法律に基づいて罰則を科せられてしまいます。シフトを作成する場合は、労働基準法を守ることが大前提となります。
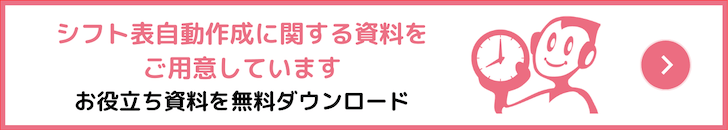
パワハラと思われないシフトを作成するために意識したいことは?

パワハラと思われないシフトを作成するためには「公平性」を重視することがポイントとなります。シフト管理者としては「○○さんは仕事が良くできるので、他のスタッフよりも多めに出勤してもらいたい」と考えることがあるかもしれません。しかし、特定のスタッフだけ多めに出勤させてしまうと、そのスタッフは「これはパワハラではないか?」という気持ちになりかねません。
見方を変えれば、公平性を欠いたシフトを作成するとスタッフからパワハラととらえられる可能性が高まるということです。スタッフにとって働きやすい環境を維持するためにも、公平性を保ったシフトの作成を心がけましょう。
シフトを作成するときに、特定のスタッフだけ出勤日を増やしたり、あるいは減らしたりした場合や、夜勤などの負担が大きい働き方を連続させた場合は、スタッフからパワハラと受け止められることがあります。できあがったシフトを見て、スタッフがパワハラだと思わないようにするためには、シフトを作成する時間を十分に確保して、それぞれのスタッフにとって偏りのないシフトを作成することが基本となります。しかし、実際にはシフトの作成に時間をなかなかかけられないのが現状といえるでしょう。シフト管理サービスを導入して、スタッフにとって偏りのないシフトを作成し、働きやすい環境づくりに努めましょう。



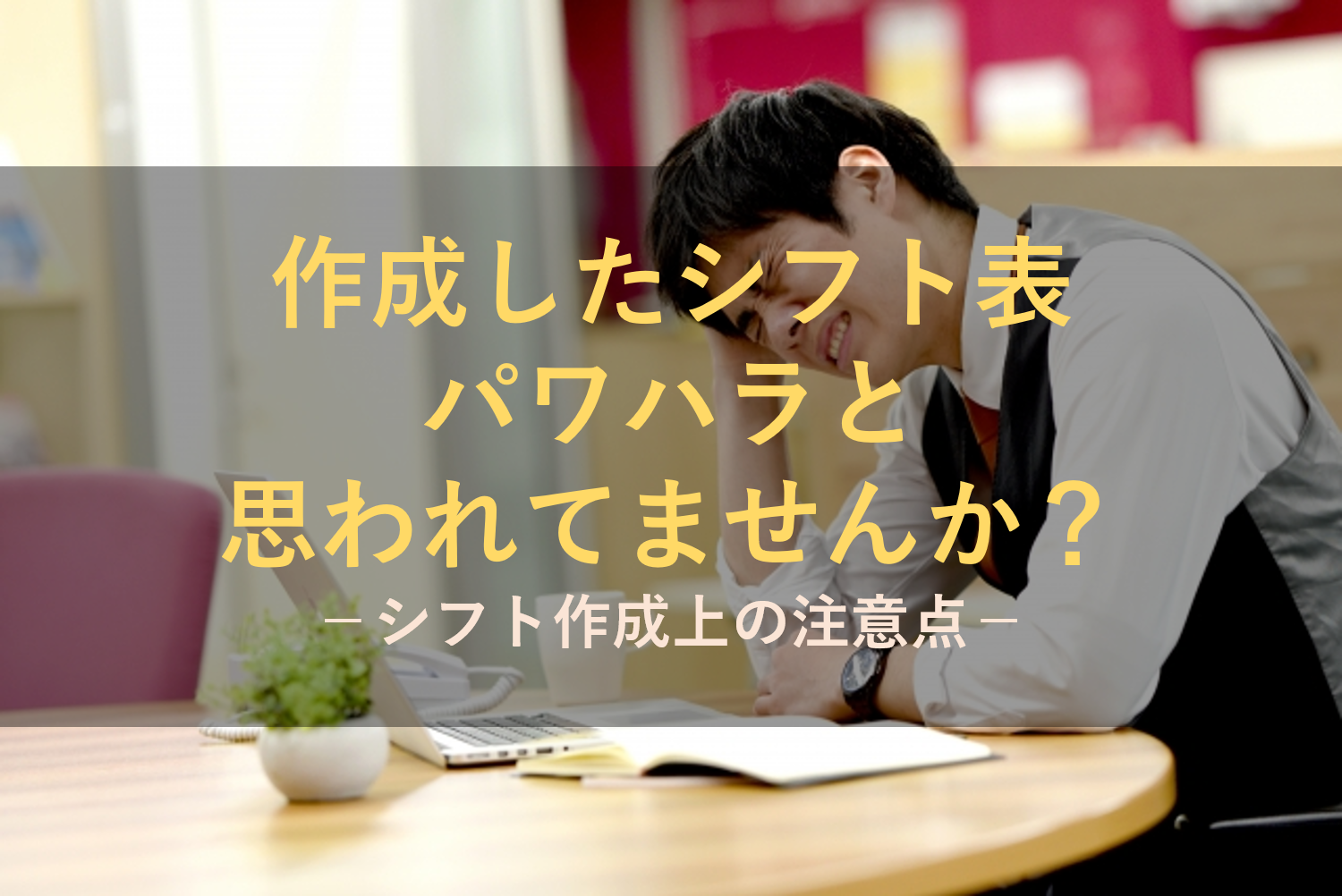 シフト作成者にとって、シフトの作成は手間がかかる作業です。本部から指示された人件費予算に基づいて、現場のオペレーションをスムーズに回すためにも、適切なシフトを作成しなければなりません。やっとの思いでできあがったシフトをスタッフに公表すると、スタッフの中にはパワハラと感じてしまう人がいる場合もあります。
シフト作成者にとって、シフトの作成は手間がかかる作業です。本部から指示された人件費予算に基づいて、現場のオペレーションをスムーズに回すためにも、適切なシフトを作成しなければなりません。やっとの思いでできあがったシフトをスタッフに公表すると、スタッフの中にはパワハラと感じてしまう人がいる場合もあります。