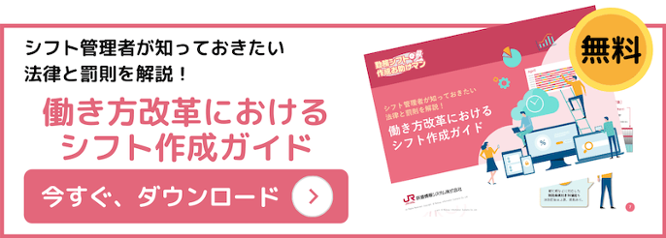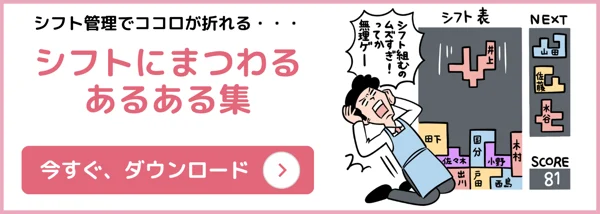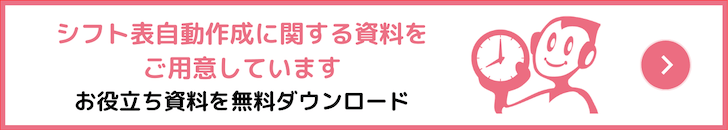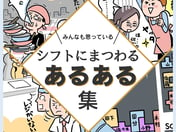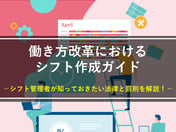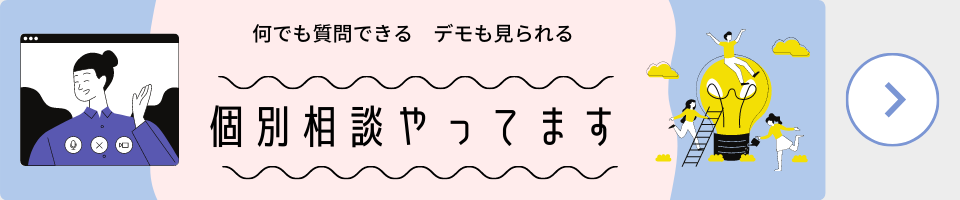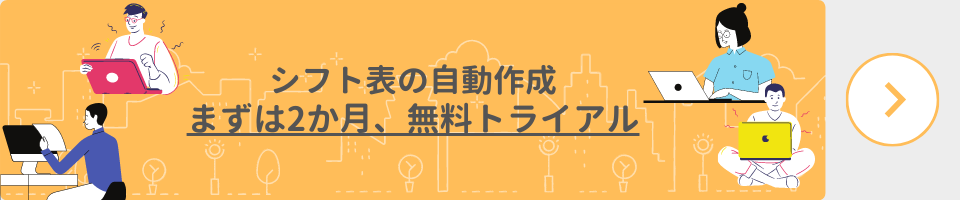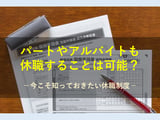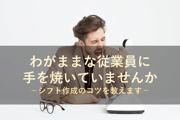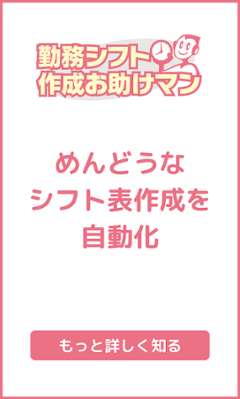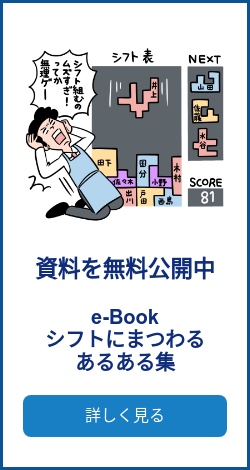少子高齢化や人口減少が進む中、働き手として社会を支える労働生産人口の減少傾向はいっそう顕著となっています。そうした貴重な年代の人々が、高い就労意欲をもっているにもかかわらず、さまざまな事情で能力を活かして働けないのは、本人にとっても、企業や社会にとっても非常に大きな損失です。
そのため、昨今はそうした人々が働きやすい仕組み、離職を選ばなくとも済む仕組みを整えることを目的とした法改正などの施策が積極的に実施されてきました。
2024年5月の育児・介護休業法と雇用保険法の改正も、こうした流れの中で実施された重要なもののひとつです。内容を正しく理解し、事業主や担当者も対応を進めねばなりません。しかし頻繁な変更と法律ゆえの難解さから、何がどう変わったのか、どう対処すべきなのか、理解しづらく困っている方も多いでしょう。そこで今回はこれらの改正ポイントを分かりやすく解説します。
育児・介護休業法および雇用保険法が改正

近年は高齢化が深刻に進むとともに、人々の間でも家族のあり方や働き方、生き方に対する志向が多様化し、それぞれの意思を尊重した雇用・就労形態、ライフワークバランスへの配慮が強く求められるようになっています。
ライフステージの変化があっても、自分らしく働き続けられる仕組みを整え、個々の能力を引き出したり、継続的なキャリア形成を支援したりすることは、国にとっても企業にとっても、その活力を維持するために欠かせません。
そうした考え方のもと、法改正も進められていますが、育児・介護休業法および雇用保険法については、とくに度重なる改正が実施されているほか、企業実務に与える影響も大きいため、現場対応としては複雑化を増す一方と感じられていることでしょう。
しかしいずれも必要な対応ですから、効率良く情報を収集し、内容を整理して迅速に対処していかねばなりません。まずは基本から確認し、直近の改正に対応した環境整備を進めましょう。
▼あわせて読みたい記事
シフトに困っている人に勧めたいシフト管理システム・アプリ
自動作成を特長とするシフト管理システム|導入する前に知っておくべきこと
シフト作成に特化したシフト管理システム比較|クラウドのメリットとは
育児・介護休業法改正とは

育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者に関する法律」といい、育児や介護を担う人の仕事と家庭の両立をサポートするために設けられたもので、各種休業・休暇制度や労働者に対して行うべき支援・配慮などを定めています。
育児や介護は現代社会における課題も多く、注目度の高い分野ですから、法改正も活発になされており、その都度新しく事業者に義務として課される内容も多数挙げられるようになっています。よって改正内容と必要対処、事業に及ぼす影響など、必要情報をタイムリーに入手し、キャッチアップしていくことが重要です。
育児・介護休業法改正の目的
今回の育児・介護休業法における改正は、男性と女性のどちらもが、ともに自身の仕事と育児や介護を両立できるようにするため、制度面や環境面の整備を進めることを目的としています。
その観点から、育児では、より実態に即した対応ができるよう、子どもの年齢に応じた労働者の働き方に関するニーズを把握し、それを実現するための措置を講じて、無理なく両立できるような働き方の選択肢を増やすこと、より柔軟な働き方を可能にすることが目指されています。
また、企業によってバラつきの目立つ育児休業取得などについて、その平準化を図り、誰もが恩恵を受けられるようにすることもポイントになりました。
介護面では、介護負担増大による離職を防ぐことがまず目的とされ、その両立を容易にするための対応や環境整備を広く、確実に実施していくことが目指されました。
育児・介護休業法改正のポイント
今回の育児・介護休業法における改正は、2024年5月31日公布となり、2025年4月以降に施行となります。ただし一部、公布日より施行となっているものもありますから、注意が必要です。
改正における変更が施された主なポイントは、大きく3つです。3つそれぞれの内容について、以下詳しく解説します。
1.子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の充実
1つ目は、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充です。これは、子どもの成長に従い、フルタイムで働く希望をもつ人も多くなってくるものの、残業は避けたいケースや、より柔軟な働き方を望むケースも増えると考えられ、それらに対応することで、男女ともが仕事やそこでのキャリア形成と育児とを両立していけるようにすることを目的としています。
まず、3歳以上~小学校就学前の子どもを養育する労働者においては、職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方が可能になるよう必要措置を講じ、労働者が選択してその仕組みを活用できるようにすることが事業者に義務付けられるものとなりました。
ここでの措置としては、始業時刻等の変更、月10日のテレワーク、保育施設の設置運営など、年間10日の養育両立支援休暇付与、短時間勤務制度の5つのうち、2つ以上を選択し設定するように求められています。労働者はこれらの中から1つを選んで利用します。
なお、テレワークなどと養育両立支援休暇については、原則として時間単位で取得可能とするよう求められ、措置設定に際しては、過半数組合などからの意見聴取の機会を設けること、3歳になるまでの適切な時期に面談などでニーズを汲み取ること、テレワークにおける労働時間管理などの面で心身の健康にも配慮することも必要とされました。始業時刻の変更などには、フレックスタイム制や時差出勤といった制度の導入が含まれます。
こうした事柄について、対象労働者への個別の周知と意向確認も事業者の義務になります。また、個々の労働者が措置についての申し出を行ったことや、措置を実施したこと、伝えた意向内容などを理由に、その労働者に対し解雇やその他不利益となるような取り扱いをすることは認められません。
第2に、所定労働時間を超える労働、いわゆる残業が免除される対象範囲が拡充となり、現行法の3歳までから小学校就学前の子どもを養育する労働者まで含まれるようになります。
第3には、子どもの看護休暇を学級閉鎖や行事参加などの場合にも利用し取得できるものとすること、そして対象の範囲を現行の小学校就学前から小学校3年生にまで拡大すること、そして勤続6カ月未満の労働者を労使協定に基づいて除外するとしていた仕組みを廃止することも決まりました。
看護休暇は、子どもが負傷したり疾病にかかったりした場合、その世話を行うためにとれる休暇で、1年度あたり5日、対象の子どもが2人以上の場合は10日まで取得できるものです。上記の取得事由と対象となる子どもの範囲拡充、除外労働者にかかる仕組みの改変により、これまでより幅広いシーン・労働者が、この休暇を効果的に取得可能になると考えられています。ちなみに変更に伴い、名称も「看護等休暇」に見直されます。
第4に3歳未満の子どもを養育する労働者で育児休業をしていない人においては、テレワークなど在宅勤務の措置を講ずることが事業者の新たな努力義務になります。努力義務であるため罰則などはありませんが、積極的に導入し両立支援を行うことが求められるでしょう。
第5には妊娠・出産の申出時や子どもが3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取を行うこと、またその意向に配慮することが、事業者の義務となりました。
2.育児休暇の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
改正法の2つ目のポイントは、育児休業の取得状況に関する公表義務の拡大や次世代育児支援対策の推進・強化を図るものです。
具体的には、第1に育児休業の取得状況について、公表するよう企業に義務を課すものを、現行の常時雇用する労働者数1,000人超の企業から、常時雇用労働者数300人超の企業まで含むように拡充します。対象となった企業は、毎年1回以上、自社における育児休業取得状況について公表しなければなりません。
公表すべき内容は、公表の前事業年度における育児休業などの取得割合か、育児休業などと育児目的休暇の取得割合のいずれかになります。前者は「育児休業などをした男性労働者数」を「配偶者が出産した男性労働者の総数」で除したもの、後者は「育児休業などを利用した男性労働者数に小学校就学前の子どもの育児を目的とした休暇制度を用いた男性労働者数の合計」を「配偶者が出産した男性労働者の総数」で除したものにより算出します。
第2、第3には次世代育成支援対策推進法に関する改正と関係するもので、この法律の延長とその実効性をより高めるための内容が挙げられています。
この次世代育成支援対策推進法というのは、急速に進む少子化や、家庭及び地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、次代を担う子どもの健全な育成を支援する環境を社会全体で整備していくため、対策を迅速かつ重点的に推進しようと設けられた時限法です。
こうした子どもの育成の観点でみると、労働者による育児休業の取得を促進し、仕事と育児を両立しやすくすることは非常に重要なことです。よって同法により、事業主は育児休業の取得状況や労働時間の状況などから改善すべき点を分析し、より良い状態を作っていくための行動計画策定が必要とされてきました。
今回の改正では、常時雇用労働者100人超の企業に対し、行動計画を策定する際、育児休業の取得状況などに関する状況把握とともに、具体的な数値目標を設定することが新たに義務付けられました。男性の育児休業取得率やフルタイム労働者の各月時間外・休日労働時間などの数値目標を示すことが必要で、制度利用時の業務分担や代替要員確保に関する方針、復帰後のポジションに関する納得感向上に向けた取り組みについて、育児の面からの労働に関する時間帯や勤務地にかかる配慮についてなど、行動計画に盛り込むことが望ましい内容も提示されました。
対象企業はこれらを含む行動計画を策定し、都道府県労働局への届出や公表・実施を行って、計画終了時に目標を達成できたかどうか確認、基準を満たせば厚生労働大臣による認定を受けられます。計画終了時点で見出された問題点については、新たな行動計画の策定に反映させるべきとされ、PDCAサイクルを確立して改善に努めねばなりません。
なお義務からは外れる常時雇用労働者数が100人以下の企業も、努力義務とされていますから、一定の対応を進める必要はあるでしょう。
そして第3にあたるものとして、この次世代育成支援対策推進法は、法改正以前には2025年3月31日までの時限法で、この時をもって失効する予定でしたが、改正により2035年3月31日までと10年間の延長が決定されました。
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
3つ目のポイントとなるのは、介護離職防止に関するものです。具体的には次の3つの変更が行われるものとなりました。
第1に、介護休業制度や仕事と介護の両立支援制度について、それらを十分に活かせず離職を選択してしまわないよう、周知の浸透や利用促進を図る目的で、以下のような措置がとられることとなりました。
労働者が家族介護に直面したことを申し出た場合には、介護休業や両立支援の制度について、事業者が個別に周知し、意向確認を行うことが義務となっています。また、事業者は40歳に達した労働者などに対し、これら制度の情報提供を早期に実施することも義務として負います。そして事業者は、労働者から介護休業の申出が円滑に行われるよう、研修実施や相談体制整備など雇用環境整備の措置も講じねばなりません。
第2には、介護を行いながら就労する場合、その労働者がテレワークを選択できるようにすることが、事業者の努力義務となりました。努力義務であり罰則はありませんが、在宅勤務などによって働きやすい環境を積極的に整えることで、両立を支援するよう求められるものとなっています。
第3には、介護休暇の取得対象者にかかる拡大が含まれました。介護休暇とは、要介護状態にある家族の世話を行うために必要なものとしてとる休暇のことで、配偶者やその父母、自身の父母、子ども、祖父母、兄弟姉妹、孫といった家族のいずれかが介護を要する場合、労働者は1年度あたり5日、対象者が2人以上の場合は10日を限度に、介護休暇を取得できます。
この介護休暇申請は、勤続6カ月未満の労働者の場合、労使協定に基づき取得対象外とできるとされていましたが、この除外の仕組みが廃止され、勤続期間にかかわらず全労働者の権利として認めねばならないことが明記されました。
雇用保険法とは

雇用保険法とは、雇用保険制度に伴って整備された法律で、労働者を雇用する事業者には、原則として強制的に適用されるものです。事業者は対象労働者を必ず雇用保険に加入させる必要があり、会社の事業規模や業種を問わず、事業主が雇用保険の適用事業所として管轄ハローワークに届出を行い、雇用保険料の納付と各種必要届出を完了させねばなりません。
雇用保険法は1947年制定の失業保険法に代わるかたちで1974年に制定されて以来、何度も改正され、その内容を更新してきています。時代や社会の情勢を反映させながら、労働者の生活や職業的な安定を図ってきたものといえるでしょう。
雇用保険法の目的
雇用保険法は、労働者の生活と雇用の安定、就職の促進を図るほか、労働者の職業安定に資するよう失業予防を行うこと、また雇用状態の是正や雇用機会の増大、労働者の能力開発、その他労働者の福祉増進を図っていくことを目的としています。
また、労働者が失業した場合や、雇用継続が困難となるような事態が生じた際には、必要な給付で支えるほか、労働者自身が職業関連の教育訓練を受けた場合にその支援給付を行うことで求職活動を容易にしたり、就職を促したりすることも、この法律の役割であり制定目的です。
雇用保険法のポイント
雇用保険法は雇用保険制度について定めているため、この制度の基本概要をつかんでおくことが大切です。
雇用保険は政府管掌の保険制度であり、労働者が1人でもいる事業所であれば、一部の農林水産を除き原則すべてが適用対象になるものです。適用事業所は、雇用保険料を納付し、規定に沿った各種届出を行う義務を負います。雇用保険料は、賃金総額と保険料率で決まっており、労働者と事業主の両方で負担します。
雇用保険の被保険者は、企業の労働者で、一定の加入条件を満たすと希望にかかわらず被保険者となります。ただし企業の代表や役員、個人事業主らは対象になりません。しかし役員と同時に部長や支店長、工場長など従業員としての身分ももっており、服務形態や賃金、報酬などからみても、労働者的性格が強いと判断され、雇用関係が認められる場合には、雇用保険に加入する被保険者となります。
被保険者となる条件においては、雇用形態が正規か非正規かは問いません。1週間の所定労働時間が20時間以上で、同一事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合、条件を満たすとされます。季節的に雇用される労働者や昼間学生など、例外もありますが、ほとんどの労働者が該当すると考えられるでしょう。
雇用保険に加入すると、労働者は求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業給付といった給付金を受け取れるようになります。
求職者給付とは、就職の意思と能力がある労働者が失業した際に、失業期間中の生活と再就職のための活動支援のため給付されるもので、失業保険などといわれるのは、この給付の基本手当部分をいいます。65歳以上での失業の場合は、高年齢求職者給付金を受給するものとなります。
就職促進給付は、再就職とその後の継続勤務を支援するための給付金で、基本手当の給付期間を残して再就職した場合に支払われます。教育訓練給付は、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が支給されるもので、失業者だけでなく在職者にも適用でき、能力開発やキャリア形成支援を目的としています。
雇用継続給付は、家族の介護などで就労できない人や、定年後の再雇用、再就職で得られる給与が大きく減った高年齢労働者を支えるものです。家族の介護で休業した被保険者で要件を満たす場合には、介護休業給付が支給され、こちらの申請は休業期間終了後、被保険者本人ではなく事業主が行います。
育児休業給付は、子どもを養育するために休業した労働者の生活と雇用安定のために支給されるもので、育児休業期間終了後、職場復帰することを前提としており、申請手続はこちらも本人でなく事業主が行うのが原則となっています。男女関係なく要件を満たせば支給され、実子だけでなく養子・特別養子縁組の場合も対象となります。
雇用保険で支えられるのは労働者だけでなく、企業も同様で、助成金や奨励金の仕組みがあります。雇用安定や職場環境改善、労働者の能力開発などに努めた場合、要件を満たすと支払われるもので、多岐にわたる制度があり、厚生労働省のサイトから検索・確認することが可能です。なお、雇用関係助成金を受給する企業の場合、労働生産性向上などの要件も満たせば、労働関係助成金の割増も受けられます。
こうした保険制度を基本内容として定める雇用保険法ですが、法改正により保険料率の変更が実施されたり、新たな企業対応が求められるところとなったりすることがしばしばあり、その動向には十分注視しておかねばなりません。
直近の2024年における改正では、5月17日に雇用保険法等の一部を改正する法律が、6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、その内容の多くは2025年4月より施行となります(一部例外あり)。
主に、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築すること、「人への投資」を強化するため雇用保険の適用拡大や教育訓練・リスキリング支援の充実化を図ること、育児休業給付における安定的財政運営の確保など、さらなる共働き・共育ての推進といった点がポイントになっています。以下、具体的に見ていきましょう。
雇用保険の適用拡大
現行の雇用保険法適用対象者として、一般被保険者となるには、1週間の所定労働時間が20時間以上で、同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがあることが必要となっています。
今回の改正では、昨今の労働者における働き方や生計維持のあり方の多様化を受け、雇用のセーフティネットを広げる必要があると判断されたことから、この要件が緩和され、1週間の所定労働時間が10時間以上の労働者にまで対象を拡充することとなりました。
ここでいう1週間の所定労働時間とは、祝日や夏期休暇などの特別休暇を含まない通常の週において勤務すべき時間のことを指し、労働時間が変動しやすく、通常週の所定労働時間が一様には換算しにくいケースでは、加重平均により算定するとされ、所定労働時間を1カ月単位で定めている場合には、その時間を12分の52で除し、1週間として算出すると規定されています。
この改正に伴って、現在の被保険者期間の算定基準も賃金支払いの基礎となった日数が11日以上から6日以上へ、賃金支払いの基礎となる労働時間数が80時間以上から40時間以上にそれぞれ変更されます。また、失業認定基準も、労働していても失業日と認定する基準がこれまでの1日4時間未満から2時間未満に変更されることとなりました。
こうした変更は2028年10月1日からの施行予定で、1週間の所定労働時間が10時間以上であるために新しく雇用保険法の適用対象となる労働者は、現行の被保険者と同様に雇用保険の各種給付が受け取れるようになります。また求職者支援制度の支援対象でもあり、そこから除外されることはありません。
教育訓練やリスキリング支援の充実
労働者が安定した再就職活動を展開できるようにするほか、労働者の主体的で積極的な能力開発、リスキリングを支援する取り組みを強化、推進するため、雇用保険による給付制限期間の見直しや教育訓練給付の拡充も、今回の改正に含まれています。詳細内容を見ていきましょう。
第1に、自己都合で退職した人が失業給付を受給する場合、現行法では7日間の待機期間満了翌日から原則2カ月間(5年以内に2回を超える場合には3カ月間)の給付制限期間が設けられていますが、雇用の安定や就職促進に必要な職業関連の教育訓練などを自主的に受けた労働者においては給付制限を行わず、給付を受け取れるようにするものとなりました。
現在もハローワークの受講指示を受け、公共職業訓練などを受講した場合、給付制限が解除されるものとなっていましたが、自身で教育訓練を実施しても解除されることになります。また、給付制限を受ける場合も、その期間が2カ月から1カ月に短縮されることも決まっています。ただし5年間で3回以上の自己都合離職の場合には、これまで同様に給付制限期間は3カ月となります。これらは2025年4月1日からの施行です。
第2に、厚生労働大臣指定の教育訓練で費用の一部を支給してもらえる教育訓練給付について、給付率上限を受講費用の70%から80%に引き上げることが決まりました。20%以上70%以下の範囲内で定められる給付金額となっていたところ、80%以下まで幅が広がります。
現行の内訳としては、雇用保険法施行規則により、中長期的なキャリア形成につながる専門的で実践的な教育訓練講座を対象とする「専門実践教育訓練」にあたるものを受講した場合の本体給付が50%で、さらに資格取得などを行った場合には20%の追加給付がなされます。また、速やかな再就職や早期キャリア形成に資する教育訓練講座とされる「特定一般教育訓練」を受けた場合の本体給付は40%となっています。こちらには追加給付はありません。
改正後は、専門実践教育訓練を受け、それにより賃金が上昇した場合、現行の給付に加えてさらに10%の追加給付を行うものとなります。また、特定一般教育訓練を受け、資格を取得、さらに就職などができた場合、10%の追加給付がなされるものとなりました。施行は2024年10月1日からとなっています。
第3に、新たな仕組みとして教育訓練休暇給付金が設けられます。現行では労働者が教育訓練に専念するため、自発的に休職するなど労働から離れた場合、その間の生活費などを支援する仕組みがありませんでした。
これを改善し、主体的で積極的なリスキリングを支援し、離職者などを含めて広く労働者が経済的な不安なく教育訓練に専念できるよう、失業保険の基本手当に相当する額の給付として、教育訓練休暇給付金を支給することとなりました。
雇用保険の被保険者で被保険者期間が5年以上ある人が、無休の休暇を教育訓練のために取得した場合、離職時に支給される基本手当額と同じ金額を、被保険者期間に応じた所定の期間、受け取れるようになります(期間は90日、120日、150日のいずれか)。国庫負担は給付に要する費用の4分の1または40分の1で、基本手当(失業保険)と同じです。
この給付制度新設に関する内容の施行は、2025年10月1日からとされています。
育児休業給付に関わる安全的な財政運営の確保
育児休業給付については、育児休業の取得者数が増えることで、支給額が年々増加していることを受け、さらなる男性育休の大幅取得増にも耐えられる安定した財政運営を支えるべく、法改正で仕組みの見直しがなされることとなりました。
具体的には、まず2024年度から国庫負担割合を現行の80分の1から8分の1に引き上げます。これは本来法律で8分の1とされたところ、暫定措置として80分の1に抑えられていたものが解除・廃止されるかたちでの実施となります。この施行は、公布日である2024年5月17日からです。
また、現行の保険料率は0.4%でしたが、当面はその割合で据え置くものの、今後の保険財政悪化に備え、本則料率を2025年度から0.5%に引き上げることが決まりました。実際の保険料率は財政状況に応じて弾力的に調整可能となります。こちらの施行は2025年4月1日からとなっています。
その他雇用保険制度の見直し
このほかにも2024年度末までの暫定措置とされてきたものの見直しや、就業促進手当に関する見直し改正が含まれました。
現行では、雇止めによる離職者の基本手当給付日数にかかる特例と地域延長給付、45歳未満の人が訓練受講中に受ける教育訓練支援給付金を基本手当の80%とする仕組みは、2024年度末までの暫定措置でしたが、この内容が見直され、前2者は2年間延長されることが決まりました。教育訓練支援給付金に関しては、給付率を基本手当の60%に引き下げますが、こちらも制度として2年間の延長が決定しています。
雇止めによる離職者の基本手当給付日数は、基本は90日~150日ですが、暫定措置として90日~330日となっており、2年間この仕組みが延長されます。地域延長給付は、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長を行う仕組みで、これも延長となりました。
教育訓練支援給付金は、初めて専門実践教育訓練を受講し修了する見込みのある45歳未満の離職者を対象に、その支援として基本手当日額の80%を受講中、2カ月ごとに支給する措置が取られてきました。改正後は2年延長し、基本手当日額の60%を2カ月ごとに支給するとされます。
就業促進手当については、現行では安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の手当として就業手当があり、また早期再就職して離職前の賃金から再就職後賃金が低下していた場合に、その低下した賃金の6カ月分を支給する手当として就業促進定着手当が設けられていますが、就業手当については廃止、就業促進手当は上限を支給残日数の20%に引き下げることが決まりました。
就業手当の廃止は、現在支給実績が非常に少なく、人手不足の状況下で安定した職業への就職をより促していくことが求められるとの判断から決定されています。就業促進定着手当は、人手不足の中で賃金低下が見込まれる再就職にインセンティブを与える必要性は乏しいものの、早期再就職を決めた人への支援という面では一定の役割を果たしていることから、これまでの基本手当支給残日数の40%相当額(再就職手当として支給残日数の70%が支給された場合は30%)を上限とするとの決まりを、一律に20%相当額に引き下げる措置をとって手当自体は維持することとなりました。
なお、再就職手当についての変更はありません。
まとめ

今回は育児・介護休業法と雇用保険法の最新改正内容について、ポイントの解説を行いました。事業者は、中でも新たに義務化される内容に注意しつつ、変わりゆくポイントを正しく理解し、自社での対応を進める必要があるでしょう。既存の制度や社内規定の更新、雇用保険関連の事務手続増加に伴う計画的対策、現状の把握と保険料負担の増加見通しにかかる調査の実施など、各所で整備を進めねばなりません。
新たな制度について、労働者へ周知を行うことや、適切な配慮が広く浸透するよう社内研修を実施する必要も考えられます。そして多岐にわたる働き方が共存し、それらによって事業運営を進めていくには、柔軟で正確なシフト管理が今以上に求められるところとなるでしょう。
最新法制に適切に対応した人事労務管理は非常に重要なものですが、それだけ複雑で手間もかかる業務となりがちです。専用のシフト管理、勤怠管理システムを導入することは、そうした負担を軽減しつつ、働きやすい環境を整備し、企業の生産性向上と効率化を推進することにつながります。自社に合ったソリューションの活用も積極的に検討しましょう。
JRシステムが提供する「勤務シフト作成お助けマン」であれば、各休暇の取得回数や労働時間の集計はもちろん、法令遵守や働きやすさを考慮したシフト表を自動で作成することが可能です。
「勤務シフト作成お助けマン」には、早番・遅番・夜勤等の「1日1記号を割り当てるシフト表」を作成することが出来る「勤務シフト作成お助けマンDay」と、 10:00~17:30等の「時問を割り当てるシフト表」を作成する「勤務シフト作成お助けマンTime」があります。作成したいシフト表に合わせてサービスを選んでいただくことが可能です。
「お助けマン」では、本番利用時と同じ機能を2か月無料でトライアルできます。是非お試しください。