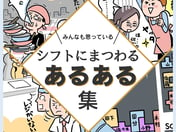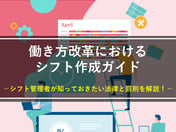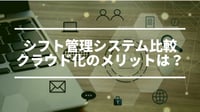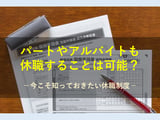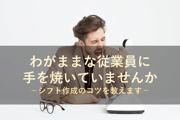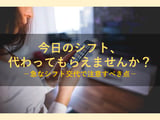「源泉徴収票」や「年末調整」は、年収が103万円以下のアルバイトでも必要になるのでしょうか。
この記事では、アルバイトの源泉徴収の基本情報と、源泉徴収票が必要な場合について詳しく解説します。
源泉徴収票とは

源泉徴収票は、企業が従業員に対して支払った給与や賞与、その給与から差し引かれた所得税の額を記載した、いわば『納税の証明書』のようなものです。
源泉徴収制度では、企業が従業員の給与からあらかじめ税金を差し引き、国に納めてくれます。
この差し引きを「源泉徴収」といい、それらを記載した源泉徴収票をもとに会社員は年末調整、個人事業主などは確定申告を行い、1年間の所得と納めた税金が正しいかどうかを精算します。そこで過不足分が調整される仕組みです。
源泉徴収票はまた、転職時の所得証明や住宅ローンを組む際などにも活用できます。
企業は源泉徴収票の発行が義務
企業は、給与を支払った従業員に対し源泉徴収票を発行する義務があります。この義務は雇用形態や年収額に関わらず適用されるため、アルバイトやパートの場合でも例外ではありません。
発行のタイミングは、年末調整後(翌年1月末まで)や退職後1か月以内と定められており、これを怠ると行政指導や罰則の対象となる場合があります。労務担当者は、発行漏れがないよう管理体制の整備が重要です。
▼あわせて読みたい記事
シフトに困っている人に勧めたいシフト管理システム・アプリ
自動作成を特長とするシフト管理システム|導入する前に知っておくべきこと
シフト作成に特化したシフト管理システム比較|クラウドのメリットとは
アルバイトの年末調整

年末調整は、1年間に支払われた給与額に基づいて源泉徴収された所得税を再計算し、過不足を精算する仕組みです。そのためアルバイトでも年末調整が必要になる場合があります。
どのようなケースで年末調整が必要なのか、また不要なのかを説明していきます。
年収103万円以下なら年末調整は不要
アルバイトの年収が103万円以下であれば、基本的に年末調整を行う必要はありません。この理由は、給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円を合計した103万円以下の場合、所得税が課されないためです。
そのため、源泉徴収される所得税自体が発生しないケースが多く、年末調整を行う理由もありません。ただし、年収が103万円以下の従業員についても、企業は給与支払報告書を自治体に提出する義務があるため手続き漏れがないよう確認しましょう。
年収103万円以下でも年末調整が必要になるケース
年収が103万円以下であっても、一定の条件下では年末調整が必要になる場合があります。例えば、従業員が他の収入を得ている場合や、複数のアルバイト先で働いている場合が該当します。
特に2つ以上の勤務先がある場合、主たる勤務先で年末調整を行うため従業員は他の勤務先で発行された源泉徴収票を提出する必要があります。
また、扶養控除や配偶者控除を受ける場合も年末調整が必要となるため担当者が適切な指導を行いましょう。
年収103万円以上でも年末調整ができないケース
一方で、年収が103万円を超える場合でも、年末調整ができないケースが存在します。例えば、年の途中で退職した場合や、複数の勤務先で働いており、いずれの勤務先でも主たる給与として申告していない場合がこれに該当します。
またフリーランスとしての収入を得ている場合や、不動産所得など他の所得がある場合も年末調整の対象外となります。こうした場合には、従業員が自ら確定申告を行い、所得税の精算をする必要があります。
特に退職者の場合は退職時に源泉徴収票を発行し、確定申告に必要な情報を漏れなく提供することが重要です。確定申告が必要な従業員には、その手続きについて適切に案内するのは労務担当者の責務となります。
年末調整の必要書類と手続き方法
年末調整を行う際にはいくつかの書類が必要となります。代表的なものとして、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除申告書が挙げられます。
これらの書類には、従業員の扶養家族や配偶者に関する情報、支払った保険料や住宅ローンの情報などが記載されます。従業員から書類を提出してもらう際には不備がないかを確認し、必要に応じて修正や再提出を依頼しましょう。
手続きは通常、年末までに完了することが求められ、翌年の1月末までに源泉徴収票を発行する流れとなります。また、手続きをスムーズに進めるためには、従業員への事前の案内や、必要書類の早期配布が効果的です。
アルバイトが源泉徴収票をもらえるタイミング

アルバイトとして働いている場合でも、源泉徴収票は必ず発行しなければなりません。源泉徴収票を発行するタイミングは主に2つあり、一つは年末調整後、もう一つは退職日以降の一定期間内です。
適切に手続きを行うためにも、それぞれのタイミングについて詳しくみていきましょう。
年末調整後
アルバイトが現在も勤務している場合は、源泉徴収票は年末調整後に発行されます。具体的には、企業が従業員の年末調整を完了させた後、翌年の1月末までに発行するのが一般的です。
この書類は、前年に支払われた給与や控除された税額が記載されており、確定申告が必要な場合や各種行政手続きに使用されます。
特にアルバイト従業員は、税金に関する手続きが不慣れな場合も多いため、源泉徴収票をしっかりと渡し、保管してもらうことが大切です。
退職日以降の1か月以内
アルバイト従業員が退職した場合、源泉徴収票は退職日以降1か月以内に発行する必要があります。このタイミングは法律で定められたものであり、退職者が確定申告や新しい勤務先での年末調整に備えられるよう配慮されています。
退職後に源泉徴収票を郵送する企業は、退職者に送付方法や期日についてなど確認しておきましょう。
源泉徴収票の見方

源泉徴収票は給与の支払いや税金に関する情報が詳細に記載された重要な書類です。税務手続きだけでなく、従業員自身の収入や控除状況を把握する上で非常に役立つため、アルバイト従業員にも正しく理解してもらいましょう。
人事や勤怠管理者は、従業員への説明責任やサポートを適切に行うため各項目についての知識が求められます。以下に重要な4つの項目について解説します。
支払い金額
「支払い金額」とは、従業員に対してその年に支払われた給与総額を指します。この金額には基本給をはじめ、残業代、手当、賞与なども含まれます。
社会保険料や税金が控除される前のいわゆる「総支給額」であるため、従業員が実際に受け取った金額(手取り)とは異なる点に注意が必要です。
この項目は、給与全体の規模を把握する基礎データとなるため、人事担当者は従業員に説明する際に誤解を与えないよう、総支給額であることを明確に伝えましょう。
給与所得控除後の金額
「給与所得控除後の金額」は、支払い金額から給与所得控除を差し引いた後の金額です。この金額は、従業員の課税所得額の算定基準となり、税金がこの金額をもとに計算されます。
給与所得控除は、収入に応じて一定の割合で差し引かれる控除であり、従業員の収入が多ければ多いほど控除額も大きくなります。人事担当者としては、この控除の仕組みについて従業員に説明し、課税対象額が給与総額そのものではないことを理解してもらいましょう。
所得控除の額の合計額
「所得控除の額の合計額」には、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、従業員が適用を受けたさまざまな控除の合計額が記載されています。この金額が大きいほど、従業員が支払うべき所得税額が軽減される仕組みです。
アルバイト従業員の場合、適用される控除が限定的な場合もありますが扶養控除などを利用するケースも考えられます。人事担当者は、従業員が適用可能な控除を正しく申告できるように年末調整のサポートを行いましょう。
源泉徴収税額
「源泉徴収税額」は、給与から実際に天引きされた所得税の金額を指します。この金額は、支払い金額に基づいて暫定的に算出されており、年末調整や確定申告を通じて正確な金額に調整されます。
特にアルバイト従業員の場合、年収が103万円以下であれば所得税が課税されないケースが多いため、年末調整後に所得税が還付される可能性があります。アルバイト従業員は税金に関する知識が乏しい場合もあるため、人事や勤怠管理者が積極的にサポートする姿勢が求められるでしょう。
源泉徴収票をもらえなかった時の対処法

アルバイト従業員が源泉徴収票を受け取れない場合、人事や勤怠管理者が適切に対応方法を説明し、従業員をサポートする必要があります。
源泉徴収票は税務手続きに欠かせない書類であり、発行されない状況が続くと、確定申告や年末調整に支障をきたす可能性があるからです。ここでは、源泉徴収票を受け取れなかった場合の対処法を紹介します。
辞めたバイト先に発行してもらう
アルバイト従業員が退職後に源泉徴収票を受け取れない場合、まずは退職したアルバイト先に連絡し、発行を依頼するのが基本的な対処法です。
法律では、企業は退職後1か月以内に源泉徴収票を発行する義務があるため、発行されていない場合は迅速な対応が求められます。電話やメールで依頼されるのが一般的ですが、内容を記録する手段として書面で依頼されるケースもあります。
人事担当者としては、従業員がバイト先への問い合わせをスムーズに進められるよう、具体的な依頼文のテンプレートや連絡方法をアドバイスすると良いでしょう。
税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する
アルバイト従業員が勤務先に依頼しても源泉徴収票が発行されない場合、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出するのが次の手段となります。
この届出書を税務署に提出することで、税務署からアルバイト先に対し、源泉徴収票の発行を指導する措置が取られます。届出書には、勤務先名や退職日、源泉徴収票が発行されない経緯などを記載する必要があります。
源泉徴収票が発行されない場合に起こりうるトラブルを回避するためにも、人事や勤怠管理者は迅速かつ的確に対応しましょう。
まとめ

アルバイトの源泉徴収票に関する対応は、法律を守るだけでなく、従業員の信頼を得るためにも重要な業務です。年収103万円以下の従業員の場合でも、年末調整の必要性や源泉徴収票の発行タイミングを説明し、迅速に対応しましょう。
このような業務をスムーズに進めるためには、シフト管理システムの導入が有効です。シフト作成や勤怠管理を効率化できるだけでなく、給与計算や源泉徴収票の発行といった手続きも一元化できるため、管理者の負担軽減と業務精度の向上が期待できます。システムを活用し、管理業務を効率化していきましょう。
JRシステムが提供する「勤務シフト作成お助けマン」であれば、アルバイト従業員の様々な希望勤務や勤務時間についての集計はもちろん、法令遵守や働きやすさを考慮したシフト表を自動で作成することが可能です。
「勤務シフト作成お助けマン」には、早番・遅番・夜勤等の「1日1記号を割り当てるシフト表」を作成することが出来る「勤務シフト作成お助けマンDay」と、 10:00~17:30等の「時問を割り当てるシフト表」を作成する「勤務シフト作成お助けマンTime」があります。作成したいシフト表に合わせてサービスを選んでいただくことが可能です。
「お助けマン」では、本番利用時と同じ機能を2か月無料でトライアルできます。是非お試しください。