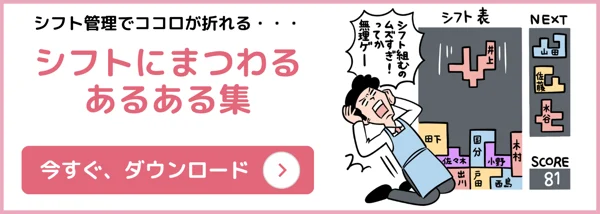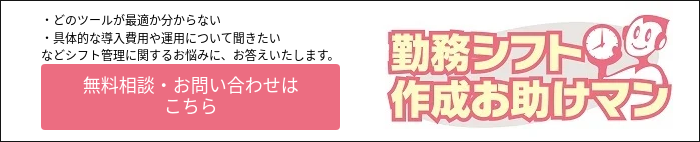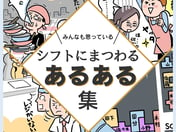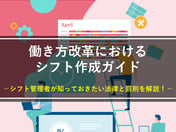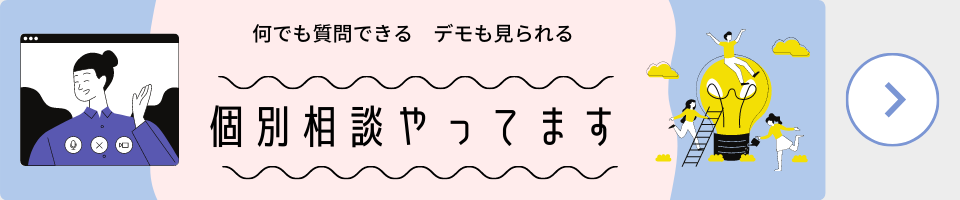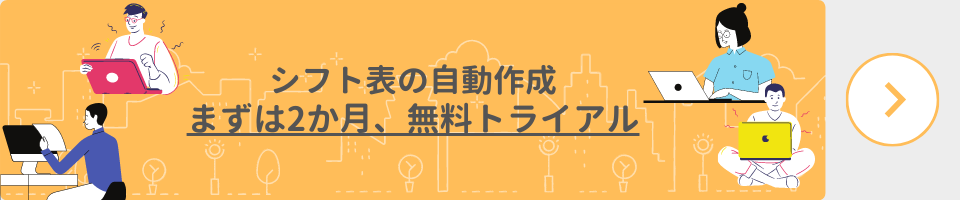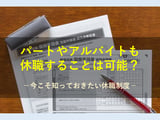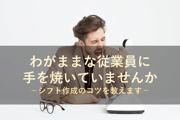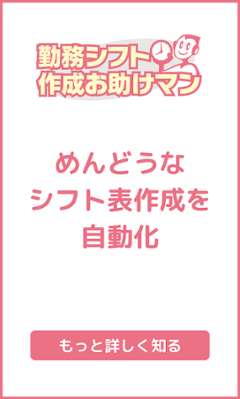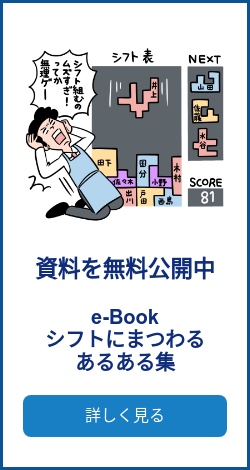「うちのシフト、7連勤だけど大丈夫?」
「繁忙期とはいえ、スタッフが限界かも…」
シフト作成の担当者なら、誰もが一度は「連続勤務は何日までOKなんだろう?」という疑問に頭を悩ませたことがあるでしょう。
実は、法律に「連続勤務は最大〇日まで」という明確な日数の上限はありません。しかし、休日の与え方や労働時間には厳格なルールがあり、これらを知らずにシフトを組むと、意図せず法律違反を犯すリスクがあります。
特に「週の起算日」や「勤務間インターバル」といった見落としがちな点が、適法か違法かの分かれ目です。この記事では、法律の基本ルールから実務での限界ライン、そして「勤務間インターバル」の重要性まで、様々な角度からわかりやすく解説します。
この記事が、貴社の休日ルールを見直し、従業員が安心して働けるシフト作りを進めるためのヒントになれば嬉しいです。
この記事でわかること
- ・連続勤務日数の法的な考え方: 法律に「最大〇日まで」という直接的な上限はないものの、労働基準法の「週1日または4週4日の休日」という原則が基本ルールとなること。
- ・一般的な上限と違法性の判断:上記の原則により、一般的には「6連勤」が上限となること。7日以上の連続勤務が違法になるかは、就業規則で定める「週の起算日」によって判断されること。
-
・実務上の限界ライン: 「4週4休」制度などを活用すれば理論上は12日以上の連勤も可能だが、時間外労働の上限などを考慮すると「12連勤」が実務的な限界の目安であること。
・日数以外の重要なルール: 勤務日数だけでなく、「1日8時間・週40時間」の労働時間上限や休憩の義務、そして従業員の健康を守るための「勤務間インターバル制度」の重要性。
・適切な労務管理の方法:雇用形態にかかわらずルールは共通であり、トラブルを防ぐために就業規則で「週の起算日」や「法定休日」を明確に定め、繁忙期には「36協定」を適切に運用する必要があること
- 連続勤務は何日まで?法的な考え方の全体像
- 「7日連続勤務」は違法?—判断の軸を整理
- 「13日・14日連続勤務」は可能か?—上限の目安
- 変形労働時間制や交替勤務でのシフト作成の注意点
- 勤務間インターバルと“実質的な連勤抑制”
- 正社員・契約社員・パートで“連勤の扱い”は変わる?
- 月またぎ・繁忙期の連勤シミュレーション
- 就業規則の書き方:週の起算日・休日特定・例外手続
- まとめ
連続勤務は何日まで?法的な考え方の全体像

法律では「連続勤務は最大〇日まで」という直接的な日数の上限は定められていません。しかし、労働基準法では「原則として週に1日、または4週間に4日以上の休日を与えなければならない」と定められています。
これが、連続勤務日数を考える上での最も基本的なルールです。この原則があるため、一般的には6日連続勤務が上限となります。
ただし、働き方によっては例外も存在します。大切なのは、この法定休日の原則をしっかりと理解し、自社のシフト作成に適用することです。
社員の健康と企業のコンプライアンス、両方を守るために、ここで正しい知識を整理しておきましょう。
関連記事:休日って具体的にはどういうもの…労働基準法上の休日の定義とは?最低年間休日や罰則を解説
「7日連続勤務」は違法?—判断の軸を整理

「7日連続勤務」が直ちに違法になるかどうかは、会社の休日ルールと「週の起算日」によって判断が分かれます。多くの中小企業で採用されている「毎週1回の休日」を原則としている場合、7日連続の勤務は違法になる可能性が高いでしょう。
労働基準法における「1週間」とは、就業規則に特別な定めがない限り「日曜日から土曜日まで」の7日間です。もしこの期間内に1日も休日がなければ、法律違反と見なされます。
例えば、日曜日を起算日とする会社で、ある社員が日曜日から次の土曜日まで7日間続けて働いた場合、その週に休日が1日もないため違法状態となってしまうのです。
一方で、「4週4休」の変形休日制を導入している場合もあります。この制度では4週間という広いスパンで休日を調整できるため、7日連続の勤務が必ずしも違法とはなりません。自社のルールを正確に把握することが重要です。
週の起算日とカウントの仕方(“月またぎ”でも同じ)
休日のカウントにおいて非常に重要なのが、「週の起算日」を明確にすることです。労働基準法における「週」とは、連続する7日間を指します。
そして「4週4休」のルールを適用する場合、この4週間の「起算日」を就業規則などでしっかりと明示しておかなければなりません。
例えば、「毎週日曜日を起算日とする」といった形で具体的に規定すれば、月をまたいでの勤務であっても、どの期間で休日をカウントするのかが明確です。
明確にすることで不必要な誤解やトラブルを防ぎ、従業員は安心して勤務でき、企業にとっても安定した労務管理が可能になります。
「13日・14日連続勤務」は可能か?—上限の目安

結論から言うと、休日付与のルール上は「13日や14日の連続勤務」も可能です。ただし、これはあくまで限定的な状況に限られます。従業員の健康への配慮などから、積極的に組むべきシフトとは言えません。
例えば、「週1日」の休日ルール(日曜日起算)を採用している会社で考えてみましょう。ある週の日曜日に休み、月曜日から翌週の金曜日まで12日間連続で勤務したとします。
そして土曜日に休むシフトを組むと、各週に1日ずつ休日があることになります。このため、休日ルール上はクリアできてしまうのです。
ただし、これは「休日」の規定をクリアしているに過ぎません。実際には、週40時間の法定労働時間を超えれば時間外労働となり、36協定の締結や割増賃金の支払いが必要です。
安易に長期連勤を組むのではなく、労働時間や健康面への影響を慎重に考慮する必要があります。無計画な連続勤務は、従業員の心身の負担を増やすだけではありません。企業にとっても大きなリスクとなるため、注意が必要です。
関連記事:法定労働時間とは?所定労働時間との違いや上限、例外規定について
実務的な“限界ライン”の考え方(12連勤目安の根拠)
理論上は、4週間に4日の休日を与える「4週4休制」を適切に運用すれば、より長い連続勤務も可能です。しかし、現実的には「12日連続勤務」が実務上の“限界ライン”となることが多く、これを「12連勤目安」と呼びます。
この根拠は、労働基準法第32条で定められた「法定労働時間」「休憩時間」「時間外労働の上限」といった複数の制約が存在することです。これらのルールをすべてクリアしようとすると、無理なく連続勤務ができるのは最大で12日程度になる、という考え方になります。
「休日を与えているから大丈夫」ではなく、時間外労働の上限や十分な休憩の確保といった多角的な視点を持つことが、コンプライアンスと従業員の健康を守る上で重要です。常に従業員の安全と健康を考慮し、法律の範囲内で無理のないシフト作成を心がけましょう。
連続「勤務時間」の上限と休憩の義務

「連続して何日まで働けるのか」という日数だけでなく「1日に何時間まで働けるのか」という勤務時間にも、法的な上限と休憩の義務が存在します。労働基準法では、原則として「1日8時間、週40時間」を法定労働時間としています。
これを超える労働は時間外労働となり、36協定の締結や割増賃金の支払いが必要です。さらに、労働時間が長くなればなるほど、休憩の取得も義務付けられています。
具体的には、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩を従業員に与えなければなりません。これは、厚生労働省のFAQにも明記されており、従業員の健康を守り、疲労を蓄積させないための重要なルールなのです。
夜勤・長時間シフトの組み方:違反しない線引き
夜勤や長時間にわたるシフトを組む際には、特に細心の注意が必要です。単に時間を埋めるだけでなく、法律に違反しない「線引き」をしっかりと理解しておくことが大切でしょう。
以下のチェックリストを参考に、安全なシフト作成を心がけてください。

厚生労働省は時間外労働の上限規制に関するガイドラインを提示しており、これに沿ったシフト運用が求められます。従業員の健康を守り、健全な職場環境を維持するために、これらの点を常に意識したシフト作成を心がけましょう。
関連記事:法定労働時間とは?所定労働時間との違いや上限、例外規定について
勤務間インターバルと“実質的な連勤抑制”

連続勤務日数の上限を考える上で、法定休日の付与は非常に重要です。しかし、それだけでは従業員の疲労蓄積や健康リスクを防ぎきれません。そこで「勤務間インターバル制度」が注目されています。
この制度の目的は、終業時刻から次の始業時刻までに一定の休息時間を確保することです。労働基準法による直接的な規制ではありません。しかし、実質的に連続勤務を抑制し、従業員に十分な休息を取らせる狙いがあります。
ここでは、勤務間インターバルの定義から具体的なシフト例まで見ていきます。さらに、避けるべきシフトパターンとその改善策も、順を追って確認しましょう。
勤務間インターバルとは(推奨時間・努力義務)

インターバル制度とは、1日の勤務終了後から翌日の始業までの間に、一定時間以上の休息時間を設ける取り組みです。従業員の生活時間や睡眠時間を確保することを目的としています。
2019年4月1日からは、労働時間等設定改善法が改正され、この制度の導入が事業主の「努力義務」となりました。つまり、法的な義務ではないものの、国が導入を推奨している重要な制度だということです。
定義
終業から次の始業までの間に設ける休息時間(9時間以上11時間未満を推奨)
目的
従業員の生活時間や睡眠時間を確保し、健康を維持する
現状
導入は企業の努力義務
勤務間インターバル制度は、単に長い連勤を防ぐだけでなく、日々の仕事の質を高めるためにも重要な役割を果たします。
関連記事:参勤務間インターバル制度について解説!一定の休息時間を与え、従業員の健康被害を予防しよう
11時間確保のシフト例(遅番⇄早番の入替)
勤務間インターバルを確保するためのシフト作成は、一見難しく感じるかもしれません。しかし、具体的な例で考えると分かりやすいでしょう。
特に、遅番と早番を組み合わせる際に意識すべきなのは、終業から次の始業までに11時間以上のインターバルを確保することです。
例えば、前日に「22時に終業した従業員」がいるとしましょう。翌日の始業を「翌朝9時以降」に設定すれば、最低11時間の休息時間を確保できます。
1日目(遅番):13:00〜22:00(休憩1時間)
2日目(中番):10:00〜19:00(休憩1時間)
このように2日目の出勤時間を調整するだけで、勤務間のインターバルは12時間となり、従業員はより十分な休息を取れます。
NG配列と改善策(遅番→早番/夜勤→日勤)
勤務間インターバルを考慮しないシフトは、従業員の心身に大きな負担をかけます。そして、健康問題や生産性の低下につながる恐れもあるのです。特に避けるべき「NG配列」と、その改善策をチェックリスト形式で確認しましょう。
【NG例①:遅番→早番】
問題点
前日の深夜近くまで働き、翌日は早朝から勤務するため、睡眠時間やプライベートな時間を十分に確保できません。
改善策
遅番の翌日は、出勤時間を遅らせた「中番」や「午後からの勤務」にするか、公休を割り当てるのが理想です。
【NG例②:夜勤→日勤】
問題点
夜勤明けは体内時計が乱れやすく、心身ともに大きな負担がかかります。十分な回復時間を取らずに日勤を入れるのは非常に危険です。
改善策
夜勤明けの日は「明け休み」とし、その翌日を「公休」にするなど、最低でも丸1日以上の休息を確保する必要があります。
改善策のチェックリスト
◻︎終業から次の始業まで、最低でも9〜11時間以上のインターバルを設ける
◻︎遅番の翌日は遅番、夜勤明けは休日を挟むなど、連続する勤務を考慮したシフト組み
◻︎シフト作成時には、従業員の希望や体調も考慮に入れる
これらの点に注意し、従業員が健康的に働けるシフト作りを目指してください。
正社員・契約社員・パートで“連勤の扱い”は変わる?

「正社員とパート社員で、連続勤務の扱いは変わるのだろうか」と疑問に思うかもしれません。結論から言うと「連続勤務に関する基本的なルール」は、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
つまり、正社員、契約社員、パートタイマーといった雇用形態は関係ありません。法定休日や法定労働時間の考え方に大きな違いはないのです。違いが生じるのは、ほとんどが雇用契約によるものです。具体的には「所定労働時間」や「勤務条件」が影響します。
例えば、「週3日勤務」契約のパートタイマーであれば、そもそも長期の連続勤務は発生しません。つまり、法律という大きな枠組みは同じですが、個別の契約条件によって実際の働き方が変わってくる、と整理すると分かりやすいでしょう。
この点をしっかり理解すれば、多様な雇用形態の従業員に対するシフト作成も、よりスムーズに行えるはずです。
雇用形態に共通する原則(法定休日・労働時間)
労働基準法が定める「毎週少なくとも1回の休日(週1休)」または「4週間を通じて4日以上の休日(4週4休)」というルールは、雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。
同様に「1日8時間・週40時間」という法定労働時間の上限も、パートタイマーだからといって例外扱いにはなりません。シフトを作成する際は「このスタッフは短時間だから」といった自己判断は禁物です。全従業員に対して、等しく法律のルールを遵守する意識を持ちましょう。
Q: 法定休日は、パートタイマーにも適用されるのですか?
A: はい、適用されます。「毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日以上の休日」というルールは、雇用形態に関わらずすべての労働者に与えなければならない法定休日です。
Q: 法定労働時間(1日8時間、週40時間)も同じですか?
A: はい、同じです。「1日8時間、週40時間」という原則は、法定労働時間の上限を定めたものです。正社員、契約社員、パートタイマーなど、すべての労働者に適用されます。
所定労働と契約条件の違い(扶養内・短時間の留意)
法律の原則は共通ですが、シフト作成時には個々の契約条件、特に「所定労働時間・日数」への配慮が不可欠です。これにより、実質的に連続勤務が制限されるケースが多くあります。
このように、法定休日や法定労働時間といった労働基準法の根幹となる部分は、雇用形態によって区別されることはありません。
所定労働と契約条件の違い(扶養内・短時間の留意)
法定休日の原則は、雇用形態にかかわらず共通です。しかし、実際の連続勤務日数の「実質的な上限」は変わることがあります。
これは、個々の契約条件や所定労働時間が影響するためです。特に、扶養内で働くパートタイマーや短時間勤務の契約社員の場合に注意が必要です。
扶養内で働くスタッフの場合
年収の上限(103万円の壁など)を超えないよう、月間の勤務時間や日数に上限を設けている場合があります。本人の希望を無視して繁忙期に連勤を依頼すると、トラブルの原因になりかねません。
短時間勤務契約のスタッフの場合
「1週間の勤務は20時間まで」「平日の4日間のみ勤務」といった契約を結んでいる場合、その条件が法律よりも優先されます。
法律を守るのは大前提ですが、さらに一人ひとりの契約内容をしっかり確認・尊重することが、円滑な店舗運営の秘訣です。
月またぎ・繁忙期の連勤シミュレーション

繁忙期や月末月初など、業務が集中する時期のシフト作成は特に頭を悩ませるものです。ここでは月をまたぐケースを想定し、安全なシフト例と陥りがちなNG例をシミュレーションします。
まずは、休日カウントの基礎となる「週の起算日」の考え方を再確認し、その上で具体的なシフトパターンを見ていきましょう。自社の現状と照らし合わせながら読み進めてみてください。
連続勤務を考える上で最も重要なのが「週」のカウント方法です。労働基準法における「週」とは、カレンダー上の月曜日から日曜日といった区切りではありません。
就業規則で定められた特定の曜日(起算日)から始まる連続した7日間を指します。このルールは月が変わってもリセットされません。
例えば、就業規則で「週の起算日は日曜日」と定めている場合、4月28日(日)から5月4日(土)までが「1週間」としてカウントされます。4月30日と5月1日では月が変わっていますが、休日管理の上では同じ週の扱いになるのです。
この「月またぎでも週のカウントは途切れない」という点を誤解すると、休日不足に気づかないまま違法なシフトを組んでしまう危険性があります。
「4週4休」の制度を活用すれば、理論上12〜13日といった連続勤務も可能です。ただし、そのためには休日以外のルールを厳格に守る必要があります。
【12連勤シフトの例(4週4休制)】
第1週:月曜から土曜まで6連勤 → 日曜休日
第2週:月曜から日曜まで7連勤
第3週:月曜から金曜まで5連勤 → 土日休日
第4週:月曜休日 → 火曜から土曜まで5連勤
この例では第1週の日曜から第3週の金曜まで12連勤が発生します。それでも4週間で計4日の休日が確保されているため、休日ルール上は適法です。
しかし、週40時間を超えた分は全て時間外労働となるので、36協定の上限に抵触しないよう厳密な管理が必要となります。
適切なシフトを作成するには、まずNGパターンを具体的に把握しましょう。その上で、改善策を講じることが重要です。繁忙期に陥りがちな、休日ルールは守っているものの、他の法律に違反しているNG例を見てみましょう。
NG例:休日は4週間で4日は確保している
問題点①
特定の週に業務が集中し、時間外労働が月45時間を大幅に超えてしまった。
問題点②
「遅番(23時退勤)→早番(翌8時出勤)」のシフトがあり、勤務間インターバルが9時間しか確保できていない。
【是正案】
対策①
一時的な応援スタッフを要請するか、36協定の特別条項(臨時的な上限延長)の手続きを労使で協議し、正式に届け出る。
対策②
遅番の翌日は必ず「休日」または「午後出勤」とし、最低でも11時間のインターバルを確保するルールを徹底する。
これらのNG例を避け、常に従業員の健康と法律遵守を意識したシフト作成を心がけましょう。
就業規則の書き方:週の起算日・休日特定・例外手続

連続勤務に関するルールを適切に運用するには、まず就業規則を正しく整備します。さらに、その内容を従業員に周知することが不可欠です。
特に、週の起算日や休日の特定、例外的な対応は必ず定めておきましょう。そうすることで労使間のトラブルを防ぎ、企業のコンプライアンス強化につながります。
ここでは、就業規則にどのように記載すればよいのか、具体的な例文を交えながら解説していきます。この内容を参考に、貴社の就業規則を見直してみてください。新たに作成する際にもご活用いただけると幸いです。
起算日の定め方と周知(例:日曜起算の条文化)
休日管理のすべての基準となるのが「週の起算日」です。これがなければ、そもそも「週1日の休日」が確保できているかの判断すらできません。休日管理のすべての基準が曖昧になってしまいます。
就業規則には、週の始まりがいつなのかを明確に規定する必要があります。
【就業規則 例文】
(週の起算日)
第〇条 労働時間および休日を計算する上での1週間の起算日は、日曜日とする。
このように、誰が読んでも解釈が一つに定まるよう、シンプルに記載することがポイントです。「うちは月曜始まり」「週末締めのサイクル」など、会社の運用実態に合わせて曜日を決定してください。この一条を定め、従業員に周知するだけで、労務管理の明確さが向上します。
会社が与える休日には「法定休日」と「所定休日」の2種類があります。割増賃金を正しく計算するためにも、これらを就業規則で区別しておくことが重要です。
法定休日
法律で義務付けられた最低限の休日(週1日 or 4週4日)。この日に労働させると35%以上の休日労働割増賃金が発生します。
所定休日
会社が任意で定める法定休日以外の休日(例:土曜日、祝日など)。この日の労働は、週40時間を超えなければ割増賃金は発生しません(超えた場合は時間外労働として25%以上の割増)
【就業規則 例文】
第〇条
休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)毎週土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日
(3)その他会社が指定する日
前項の休日のうち、毎週日曜日を法定休日とする。
このように、どの曜日が割増率の高い法定休日にあたるのかを特定しておけば、給与計算のミスや労務トラブルを未然に防げます。
特別条項付き36協定の手続と記録(繁忙期の例外)
どうしても繁忙期に対応しきれず、法定の上限を超えて残業をお願いする場合もあるでしょう。その際は「特別条項付き36協定」の締結と届出が必須となります。この手続きなしに上限を超えた残業をさせることは法律違反です。
運用にあたっては、以下の3つのポイントを必ず守ってください。
届出
まず、使用者と労働者の代表とで協定内容に合意します。その後、必ず労働基準監督署長へ指定の「様式第9号の2」を届け出てください。
上限
特別条項があっても、無制限に残業できるわけではありません。「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」「月100時間未満」という絶対的な上限は超えられないのです。
記録
従業員一人ひとりの労働時間を正確に記録してください。そして協定の範囲内であることを、いつでも確認できる状態にしておく義務があります。
これらの手続きと記録を怠ると、法律違反となる恐れがあるため、必ず適切に対応するようにしましょう。
まとめ
連続勤務に関しては、法律で明確に「何日まで」と定められているわけではありません。しかし、実際の運用にあたっては以下のような目安や考え方が基準となります。
・法律上の直接的な上限日数:定めなし
・「週1日の休日」ルールの場合:実質12連勤が上限の目安
・「4週4日の休日」ルールの場合:実質24連勤まで可能だが、現実的ではない
・違法性の判断基準: 「週の起算日」から始まる1週間に1日の休日が確保されているかどうか
・現代の重要指標:従業員の健康を守るための「勤務間インターバル」の確保
このように、形式的なルールだけでなく、従業員の健康や働きやすさを守る観点からも勤務状況を管理することが重要です。
こういった勤務に関するルールや法令に基づいたシフト作成をするツールはぜひ、勤務シフト作成お助けマンをご利用ください!